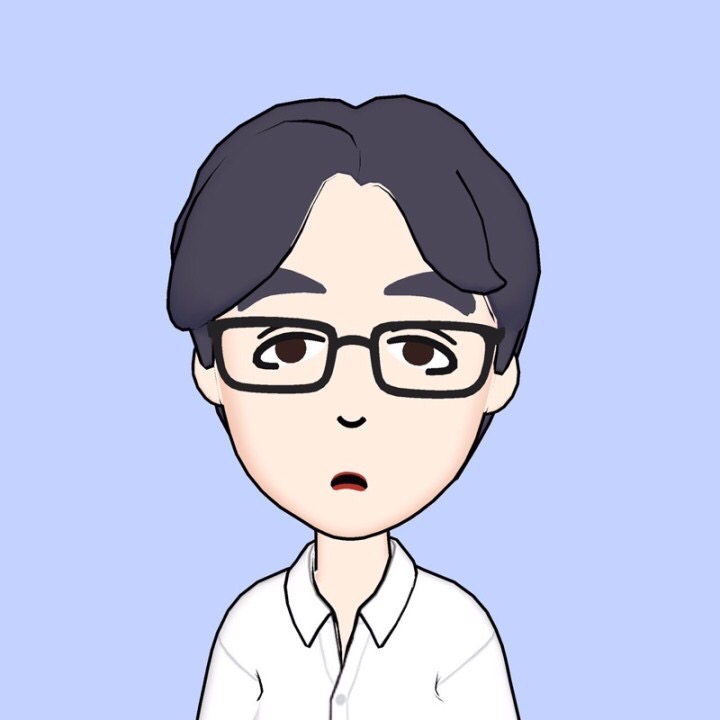雪深い山奥の館に集められた見知らぬ5人、そして謎の予告「犯人はふたり」――ミステリー好きなら思わず惹かれてしまうシチュエーションではないでしょうか。吉村達也さんの小説『王様のトリック』(双葉文庫)は、閉ざされた雪山の“要塞”で展開する極限の心理戦ミステリーです。読後には「まさかこんな展開になるなんて!」と驚く部分もあれば、「そうきたか…」と唸る部分もあり、まさに賛否両論を呼ぶ問題作とも言えるでしょう。
本記事では、作品の魅力と気になる点を大学生以上の読書好きの皆さんに向けて親しみやすくご紹介します。まず著者・吉村達也さんについて触れ、主要人物と物語の概要をネタバレ控えめにまとめます。その後、感想と深掘り考察では物語のトリックやテーマについて分析し、読者の反応もポジティブ・ネガティブ両面からピックアップ。最後に次に繋がるオススメ作品や関連グッズも紹介します。**「犯人は二人」という異色のクローズドサークル・ミステリー、その真相にあなたは辿り着けるでしょうか?**ぜひ最後までお付き合いください。
Contents
著者プロフィール:吉村達也さんについて
まず、本作の著者である吉村達也さんについて簡単にご紹介します。吉村達也(1952–2012)は日本の小説家で、1980年代から2010年代にかけて多数のミステリー作品やホラー作品を発表しました。デビュー当初は大胆なトリック重視の本格推理で注目を集め、処女作『Kの悲劇』で鮮烈なデビューを飾っています。代表作には名探偵が活躍する「朝比奈耕作」シリーズや「氷室想介」シリーズなどがあり、幅広いジャンルのミステリーを書き分けました。編集者出身という経歴から執筆姿勢も独特で、出版業界を舞台にした『ベストセラー殺人事件』のような作品も残しています。
吉村さんの作風はキャリアを通じて変化しています。派手なトリックが光る本格ミステリーを多く手掛けた一方で、次第に人間の心理ドラマを重視する傾向が強まりました。読者の意表を突くどんでん返しや叙述トリックから、登場人物の心理描写やサスペンスに重きを置いた作品へとシフトしていったのです。この背景を踏まえると、『王様のトリック』もトリックの意外性と人間心理のサスペンスを融合させた作品であることがうかがえます。本作は2010年に双葉文庫から刊行された吉村さん晩年の作品で、2005年発表の中編『ドクターM殺人事件』を加筆・改稿して長編化した経緯があります。ベテラン作家・吉村達也が**「犯人が二人いるミステリー」**という大胆なアイデアに挑んだ意欲作と言えるでしょう。
登場人物について:個性豊かな5人の“M”たち
本作に登場する主要人物は5人。いずれもお互い初対面の男性たちで、ある日突然謎の館に招かれるという役どころです。特徴的なのは全員の名前の頭文字がアルファベットの“M”で始まる点で、それぞれ異なる職業・背景を持っています。以下に彼ら5人のプロフィールと、本作での見どころを紹介します。
- 御木本(みきもと) – 人気俳優。華やかな芸能界から雪山の密室に呼ばれた異色の存在です。カリスマ性があり人当たりも良い彼ですが、演技派ゆえに本心が読みづらく、他の招待客からも「何か隠していそう」と疑われます。極限状況下で役者魂をどう発揮するのか注目です。
- 槇原(まきはら) – 僧侶。お坊さんという平和的な肩書きから、5人の中では一見もっとも穏やかで犯人らしくない人物です。冷静沈着で経典の教えを口にする場面もあり、パニックに陥る一同を宥めようとする精神的支柱的存在。しかしその落ち着きがかえって不気味にも見え、疑心暗鬼が深まる中でどのような行動を取るのか…。
- 校條(めんじょう) – 推理作家。同業のミステリー作家ということで、事件の展開に対し誰よりも推理心を燃やす人物です。豊富な知識と観察眼で状況を分析しようと努め、他のメンバーの会話の端々から違和感を探ります。探偵役不在の本作において、彼の推理作家としての勘が鍵を握る場面もありそうです。
- 水野(みずの) – プロテニスプレーヤー。スポーツ選手らしく体力があり、行動力もピカイチ。突然の雪山での監禁状態にも「何とか打開しよう」という闘志を見せます。短気で熱くなりやすい一面もあり、疑い合いが始まると感情を露わにする場面も。機敏な行動派ゆえ、もし犯人なら身体能力を活かした犯行も可能?その一挙一動から目が離せません。
- ムーア – 英会話講師。外国人の英語教師で、5人の中では異色の存在です。文化の違いからかリアクションが大げさだったり、日本人メンバーとの微妙な認識ズレが緊張感を生むこともあります。しかし語学教師だけあって議論好きで雄弁なため、他者との心理戦トークでは一歩も引きません。彼の発言が事態をかき乱すのか、それとも真相へのヒントをもたらすのか注目です。
以上のように個性も経歴もバラバラな5人ですが、冒頭でも触れた通り彼らには“ある共通点”があります。それが全員の名前頭文字「M」です(御木本=Mikimoto、槇原=Makihara、校條=Menjō、水野=Mizuno、ムーア=Moore)。なぜ彼ら5人が選ばれたのか? この**「M」に隠された意味**も物語の重要な謎の一つとなっています。
あらすじ:孤絶した館で幕を上げる“殺人ゲーム”
年の瀬も押し迫る冬、北アルプスの人里離れた山中にそびえる謎の洋館。まるで要塞のように頑丈なその建物「奇巌城(きがんじょう)」に、見ず知らずの5人の男たちが招集されます。集められたのは先ほど紹介した職業も年齢も異なる5人。招待主について心当たりがないまま館に足を踏み入れた彼らを待ち受けていたのは、不気味な真紅に塗られた部屋と一枚のメッセージカードでした。
そのメッセージにはこう書かれています。「これから殺人劇の幕が上がる。犯人はふたり」。突然の不吉な予告に5人は困惑します。外は激しい吹雪で通信手段も途絶え、もはや館から逃げ出すことも助けを呼ぶこともできません。閉ざされた雪山の館で、自分たちの中に殺人者が二人潜んでいる…!?想像するだけで背筋が凍るような状況に、5人は否応なく陥れられてしまったのです。
予告通り“殺人劇”の幕が上がるのかと怯える彼ら。しかし、疑心暗鬼はすぐに現実のものとなります。館内には彼ら5人以外に人影はなく、つまり犯人がいるとすればこの中の二人ということになります。5人は互いを探り合い、会話の端々から協力関係を匂わせる者はいないか目を光らせ始めます。それぞれ「自分は騙されないぞ」と神経を尖らせる中、早くも最初の犠牲者が発生してしまいました…。
突如起こった殺人にパニックに陥る一同。しかし犯人が一人ではなく二人いる可能性が高い以上、目の前で嘆いている人物さえ実は犯人側かもしれないのです。誰を信じればいいのか? 一番犯人らしくない人物ですら犠牲になる非常事態に、残された者たちは極度の疑心暗鬼に陥っていきます。逃げ場のない館の中、次々と明かされる5人の意外な接点や過去。そして「ドクターM」と名乗る謎の存在とは一体誰なのか…?
一夜にして**閉鎖空間と化した“奇巌城”**で、招待客たちは生き残りを懸けた疑心暗鬼のゲームを強いられます。一人、また一人と無残にも殺されていく中、果たして二人組の真犯人は誰なのか。緻密に仕組まれた《王様のトリック》と呼ぶべき犯人たちの策略の目的とは? 物語は緊張感をはらんだままクライマックスへ雪崩れ込みます。最後に明かされる真相は衝撃的でありつつもどこか虚しさを伴うもので、読み終えた後には何とも言えない余韻が残るでしょう…。※これ以上はぜひ実際に作品を読んで確かめてみてください。
(ネタバレなしで物語終盤までをご紹介するのは難しく、このあらすじでは詳細をかなりぼかしています。続きが気になる方はぜひ本編でその目でお確かめを!)
感想:緊迫の前半と賛否分かれる結末…読者目線で感じたこと
まず率直な感想として、「犯人は二人いる」という設定自体は新鮮で序盤からグイグイ引き込まれたということをお伝えしたいです。雪山の孤立無援の館という王道シチュエーションに、この作品ならではのルールが一つ加わるだけで、ここまでスリルが増すのかと驚きました。誰も信用できない密室というだけでも緊張感たっぷりなのに、「もしかしてAさんとBさんがグルでは…?」などと疑い出すとキリがない状況。読んでいるこちらも登場人物たちと一緒になって「もしやこの人とこの人が…?」と推理しながら振り回され、まるで人狼ゲームに参加しているかのような心理戦を体感できました。
本作の前半~中盤は、まさに手に汗握る展開です。吹雪で閉ざされた館内で次第に追い詰められていく恐怖、そして誰かを信じたいのに信じられない疑心暗鬼…。その緊迫感の演出はお見事でした。特に最初の事件発生からしばらくの間は「この先どうなってしまうんだ!」とページをめくる手が止まらなくなるほどで、ミステリーならではのゾクゾクするような雰囲気に浸れます。「一番大人しそうな人が真っ先に殺されてしまう」というショッキングな展開もあって、物語の歯車が一気に加速していく感覚がたまりません。
一方で、後半の真相明かしの部分には賛否が分かれそうだとも感じました。物語のクライマックスでは犯人たちの動機やトリックが明かされるのですが、その内容がやや唐突で強引に思える点があったのは否めません。序盤から丁寧に伏線が張り巡らされているタイプのミステリーではなく、最後に犯人自身の口から長々と種明かしが語られる展開なので、読者によっては「後出しじゃんけん」のように感じてしまうかもしれません。私自身、「なるほど、そういうことだったのか」と一応納得はしたものの、犯人の動機には少しモヤモヤが残りました。登場人物たちが味わったであろうやりきれなさや後味の苦さを、読者である私も追体験してしまったようです。
とはいえ、タイトル『王様のトリック』の意味を考えると、この結末にも作者なりの意図が感じられて興味深かったです。物語中で語られる「タイトル」に関するやりとりや、犯人が示す身勝手な論理などを踏まえると、単なる勧善懲悪ではないテーマが隠されているように思います。派手なトリックで読者を驚かせるというより、人間のエゴや罪の意識といった心理面に焦点を当てている点は、さすが吉村達也さんらしい作風だと感じました。結末まで読み終えたとき、「なんとも割り切れない気持ち」が残るのもまた本作の味わいであり、好き嫌いは分かれそうですが私はこれはこれでアリかな、と思います。
文章については、全体的に平易で読みやすい文体なのでスイスイ読めました。情景描写や心理描写も過度に難解な表現はなく、ミステリー小説としては比較的ライトな読み心地です。グロテスクな殺人描写も控えめで、怖いシーンでも描写が直接的すぎず程良い緊張感なので、ホラーが苦手な方でも読み進められるでしょう。その反面、「謎解き」という点では本格ミステリ的な綿密さを求めると肩透かしを食うかもしれません。探偵役不在のまま物語が進行するため、自分で手掛かりを集めて推理を組み立てる楽しみは薄く、「犯人は最初からほぼ明示されているようなもの」と感じる人もいるようです。読む際は本格推理というよりサスペンススリラー寄りの作品だと思って臨むと良いでしょう。
総じて、『王様のトリック』はアイデア勝負のエンタメミステリーとして楽しめる部分と、緻密さや爽快感に欠ける部分が同居した作品だと感じました。先の展開が気になって一気読みしてしまうような勢いは確かにありますし、「犯人が二人」という着想自体はミステリー慣れした読者でも新鮮に映るはずです。一方、物語のオチについては読後に色々と意見を交わしたくなるタイプで、「良くも悪くもB級スリラー映画を観たような気分」という印象も受けました。人によって評価が割れるのも納得ですが、読み終えた後にあれこれ考察したり語り合ったりしたくなる作品であることは間違いありません。
考察・解説:仕掛けられた謎とテーマを深掘り
ネタバレを避けつつ『王様のトリック』のポイントを考察してみましょう。最大の特徴である「犯人は二人いる」という設定は、ミステリーの常識を破る大胆なものです。一般的な推理小説では犯人は一人であることが多く、読者もその前提で手掛かりを追います。しかし本作は**「犯人が複数」という前提を最初から提示することで、既存のミステリー定石を覆そうとしている**ように見えます。この試み自体、ミステリーに読み慣れたファンほど「お、面白いことをするな」と興味をそそられる部分ではないでしょうか。
犯人が二人いる状況下では、物語の構造や読者の推理アプローチも大きく変化します。例えば通常の作品では「こいつが犯人だ!」と一人に絞り込むゲームですが、本作では**「誰と誰が共犯なのか」を組み合わせで考えねばならない**ため、可能性はぐっと増えます。作中の登場人物たちもまさにその状況に置かれ、誰か一人を疑えばその人物ともう一人の繋がりまで考えねばならず、疑惑が際限なく広がっていきます。結果、彼らは互いの一挙手一投足に神経を尖らせ、普段なら見逃すような小さな言動にも敏感に反応するようになります。読者も「もし自分がこの中にいたら誰を信じるだろう?」などと想像するとゾッとしますよね。
この構図は人狼ゲームやマーダーミステリーといった正体隠匿系ゲームにも通じるものがあります。実際、5人の中に2人の“裏切り者”がいる状況は人狼ゲームそのものですし、外界と隔絶された舞台という点はアガサ・クリスティの名作『そして誰もいなくなった』を彷彿とさせます。もっとも、本作の場合は犯人があらかじめ「二人」と明言されているぶん人狼ゲームより親切(?)ですが、それでも味方だと思っていた隣人が突然牙をむく恐怖は計り知れません。クローズドサークルものの緊張感を最大化するための一つの工夫として、「複数犯人」という設定はかなり効果的に機能していたと言えるでしょう。
もう一つ、本作で特筆すべきは登場人物たち全員の名前がアルファベットのMで始まる点です。これは読み進めるうちに読者も気づく仕掛けで、「あれ?全員Mだ…ひょっとしてDr.Mって……?」と推理を掻き立てられる要素になっています。犯人を探す鍵としてこのイニシャルの一致がどんな意味を持つのかはネタバレになるので詳しく触れませんが、少なくとも吉村達也さんが意図的に施した遊び心あるミスディレクションであることは間違いありません。ミステリー好きなら「Mってもしや○○の頭文字では?」などと色々考えてしまうところでしょう。このようにネーミングレベルから伏線を張っているのも本作のユニークな点です。
犯人たちの動機や目的について考えると、本作のテーマらしきものが浮かび上がってきます。犯人(共犯者)たちがなぜこんな狂気のゲームを行ったのか…結末まで読むと、その理由は決して大それたものではなく身勝手で歪んだものであったことがわかります。読者の中には「そんな理由で無関係な人間まで巻き込むなんて!」と憤る方もいるでしょうし、それこそが作者の狙いだったのではとも思えます。つまり、人間のエゴイズムや復讐心の空しさが浮き彫りになるよう計算されているのではないか、ということです。犯人自身の口から語られる自己中心的な論理は、到底正当化できるものではなく、むしろその理不尽さこそが読後に強い印象を残します。タイトルの「王様」とは、さも自分が絶対的権力者(=王様)であるかのように振る舞った犯人たちへの皮肉にも感じられました。彼らが仕掛けた《王様のトリック》とは、自分勝手な“王様気取り”が引き起こした悲劇そのものだったのかもしれません。
メタ的な視点になりますが、作中で編集長がタイトルについて言及する場面があります。詳細は伏せますが、その言葉を借りれば「『王様のトリック』というタイトルは内容から考えるといささか仰々しすぎるのではないか」という皮肉めいた指摘でした。まさに読者の一部が感じた「タイトルほどの凄みはなかったかも」という感想とシンクロしており、作者は自ら作品タイトルに対する批評を織り込んでいたとも受け取れます。このあたり、吉村達也さんらしいメタ的な遊びにも思え、興味深い点です。
なお、『王様のトリック』には先行作品として『ドクターM殺人事件』という中編がありましたが、これは犯人やトリックに若干の変更を加えた別バージョンのようです。改稿にあたって吉村さんが何を変え、何を伝えたかったのかを想像するのもマニアにはたまらないでしょう。例えば「犯人は二人」というコンセプトをより強調するために物語の焦点を心理戦に振ったのでは…などと推測できます。結果として本作は、推理小説というよりスリラー・サスペンス小説に仕上がっており、読み終えた後に解決編の論理よりも人間ドラマの方が記憶に残るようになっています。これはまさに前述した著者の作風変化(トリック重視から心理重視)とも合致しており、晩年の吉村作品らしい特徴と言えるでしょう。
最後に、この物語が読者に問いかけるものについて考えてみます。閉ざされた環境下で人間はどれだけ疑心暗鬼に陥るか、信頼が崩れる恐怖、そして因果応報の虚しさ…。**「人間の心の闇」**のようなテーマが底流にあるように思います。華やかな肩書きを持つ人々も極限状態では猜疑心に囚われ、理性が揺らいでしまう様は、人間心理の弱さを如実に表しています。また、犯人側の動機から浮かび上がる身勝手さは、「他者への想像力を欠いた復讐は無益である」という教訓めいたものすら感じさせました。単なる謎解きの枠を超えて、読後に人間心理について考察したくなる奥行きが本作には秘められているのではないでしょうか。
読者の反応:SNS上の声は賛否両論
『王様のトリック』に対する読者の評価は、SNSや書評サイトでも好意的な意見と否定的な意見が入り混じる形となっています。その一部をピックアップしてご紹介します。
ポジティブな反応(好評) 🟢
- 「素直に面白いと思いました。文体も読みやすいですね。」読み慣れない人でもスラスラ読める文章と、シンプルに楽しめるエンタメ性を評価する声。
- 「“犯人は2人いる”という最初の設定がおもしろかったのと心理戦、誰が犯人かわからないけど人が殺されていくという展開が面白くて3分の2くらいまではとても面白かったです。」ユニークな着想と中盤までのスリリングな展開に夢中になったという意見。
- 「登場人物が少ないため把握しやすく、先の気になる展開で中盤までの惹きつけはすごかった。」キャラが5人に絞られている分ストーリーに集中でき、物語の引力が強かったと好評。
- 「結果、B級でしたが面白かったです(笑)。」大作というよりB級スリラーのノリとして割り切れば十分楽しめる、とユーモア交じりに称賛する声。
- 「平凡だなあと思って読んでいると、2人が殺害され、残り3人となってからが面白い。」物語後半、登場人物が絞られてから一気に面白さが増したと感じた読者も。謎解きよりも人間ドラマの緊迫感に魅せられた様子です。
→ 肯定的な意見の傾向: 「犯人が二人」という着眼点の斬新さや、序盤~中盤のハラハラする展開、そして読みやすさを評価する声が目立ちました。凝ったトリック満載の本格ミステリというより、スリルとテンポの良さで読ませるサスペンスとして楽しんだ読者が多いようです。「一気読みした」「設定を聞いて思わず購入した」といったコメントも散見され、コンセプト勝ちの作品として興味を惹かれた人が多かった印象です。
ネガティブな反応(賛否両論・批判) 🔴
- 「面白くないわけではないが、意外性があまりない。伏線をたくさん張ってあるミステリーではないので、後出しジャンケン的な種明かしだ。」驚きや巧妙な伏線を期待すると肩透かしに感じるという指摘。
- 「犯人とトリックをほぼ丸出しにした形でミステリと言われても、どこに面白味を見出せば良いのか…」序盤の時点で犯人像が明示されすぎていて推理のしがいがなかった、との厳しい意見。
- 「中盤まで惹きつけられたが、犯人とその動機が明らかになるにつれて個人的に腹落ちしない部分が増えてしまった。」終盤の真相に納得できず、不満が残ったという声。動機の弱さや説明に説得力が感じられなかった模様。
- 「後半に犯人が登場して延々と動機を語るという、斬新だから面白いわけでもなく、読んでる方としても『そうですか……』以上の感想がない。」ユニークな展開ではあるものの、盛り上がりに欠ける結末だったとの指摘。
- 「叔父ももっと早く気づけよ?みたいな。結局犯人は実質1人ですし。そこが最後ずっこけなのが残念でした。」(Amazonレビューより)二人犯人という触れ込みに対し、実際は一人が主導していたように感じられ拍子抜けしたという辛辣な意見。
→ 否定的な意見の傾向: 後半の展開や真相への不満が中心でした。「序盤は良かったのに終盤でガッカリ」という声が多く、犯人の動機やトリックの見せ方に納得いかない読者が目立ちます。特に伏線不足やご都合主義的な説明に対する指摘、そして「最初から犯人を2人とバラす構成はミステリとしてどうなの?」という意見もありました。要するに、「設定倒れでもっと練れたはず」「最後がイマイチで消化不良」と感じた人が一定数いるようです。
このように本作への評価は真っ二つと言っていいほどですが、裏を返せばそれだけ語り甲斐のある作品とも言えるでしょう。設定のユニークさを買う声、物語の盛り上げ方を評価する声がある一方で、論理面の粗さや読後感に引っかかる声もあり、読者それぞれのミステリー観によって感じ方が大きく異なるようです。
次回への期待:この体験を次の読書へ活かすには
『王様のトリック』は完結した単巻作品であり、直接的な続編やシリーズ化はありません。しかし、読後には「もっとこんなミステリーを読みたい!」という好奇心が刺激されるのではないでしょうか。そこで、本作を読んだ後に感じた次への期待や、関連する読み物への誘いについてお話しします。
まず、本作で味わったようなクローズドサークルのスリルや心理戦の醍醐味を求めているなら、ぜひ他の作品にも手を広げてみましょう。たとえば、先に名前を出したアガサ・クリスティの**『そして誰もいなくなった』は孤島に招かれた客たちが一人また一人と消えていく有名な密室サスペンスです。本作に通じるシチュエーションながら犯人像は全く異なるので、「犯人は一人の場合」の緻密さ**を比較してみるのも面白いかもしれません。
また、吉村達也さんの他の作品に挑戦してみるのも良いでしょう。吉村さんは本作以外にも多数のミステリーを書かれており、謎解き要素が強いものからホラー色の濃いものまで幅広く楽しめます。特に「朝比奈耕作シリーズ」などは名探偵が活躍する王道の推理物で、本作とはまた違った読み応えがあります。もし『王様のトリック』で吉村作品に興味が湧いたなら、過去の代表作を読むことで著者の作風の変遷を感じ取れるでしょう。
一方で、「犯人が二人いるミステリー」というコンセプト自体に興奮した方は、それをテーマに友人と語り合ったり、自分なりのシナリオを想像してみるのも楽しいかもしれません。「もし自分が同じ状況に置かれたら誰を信用するか?」なんて問いかけは、飲み会や読書会で盛り上がるネタになりそうです。実際、この作品は読み終えた後に他の人と感想を交換したくなるタイプなので、SNSで検索してみると様々な推測や議論が飛び交っています。そうした読者同士のコミュニケーションも含めて、一つの作品体験が広がっていくのはミステリー小説ならではの楽しみですね。
吉村達也さんご本人は残念ながら2012年に逝去されていますが、その分多くの作品が遺産として残っています。本作で吉村作品デビューした方は、ぜひ遡って他の作品にも挑戦してみてください。きっと『王様のトリック』とは違った驚きや感動が待っているはずです。そしていずれ、「犯人が三人いるミステリー」なんてものに出会える日が来るかも…?(もしそんな作品をご存知でしたら教えてください!)読書の世界は広大で、今回のような一風変わった作品との出会いが、また新たな本との巡り会いに繋がっていくことでしょう。
関連グッズ紹介:作品世界をさらに楽しむために
最後に、『王様のトリック』を読んで興味を持った方におすすめの関連グッズや作品をいくつか紹介します。読後の世界観を補完したり、次の一冊選びの参考にしてください。
- 『王様のトリック』 (双葉文庫) – 言うまでもなく本作そのもの。双葉社より2010年に文庫発売された改稿版で、現在は電子書籍版も入手可能です。雪深い館に集められた5人の男たちと「犯人はふたり」のメッセージという惹き込まれる紹介文が帯にも記載されています。まずはぜひ本編を手元に置いて、もう一度細部まで堪能してみてください。初読時には気づかなかった伏線やヒントが見えてくるかもしれません。
- 吉村達也『ドクターM殺人事件』 (JOYノベルス) – 本作の原型となった中編小説。2005年にJOYノベルスから刊行されました。加筆改稿を経て『王様のトリック』になったためストーリーはほぼ同じですが、タイトルや細部設定の違いを比較すると興味深いでしょう。現在は入手困難かもしれませんが、古書店や図書館で探してみるのも一興です。幻の元版を読むことで、本作の進化の過程を辿ることができます。
- 吉村達也「朝比奈耕作シリーズ」 – 吉村作品が気に入った方には、代表作の一つである推理シリーズもおすすめです。大学教授の名探偵・朝比奈耕作が活躍する本格ミステリーで、トリック重視の謎解きが楽しめます。『王様のトリック』とは作風が異なり、犯人当ての醍醐味を味わえるでしょう。吉村さんの多才さを感じられるシリーズです。ミステリーの世界に浸った後は、こうした本格ものでもう一度頭をフル回転させてみてはいかがでしょう。
- 『そして誰もいなくなった』(アガサ・クリスティ) – クローズドサークルものの金字塔とも言える海外ミステリー。孤島に招かれた10人が次々と殺されていく筋立ては、本作と共通する部分も多く比較されがちです。犯人は一体誰なのか? 史上最高峰のミステリートリックと名高い結末が待っています。もし本作でクローズドサークルに目覚めたなら、原点とも言えるこの作品は必読です。異なる時代・国の作品と読み比べることで、本作の新しさや特色もより浮き彫りになるでしょう。
(他にも、劇中で感じたスリルを体験できる推理ゲームや、登場人物の職業にちなんだ書籍など、楽しみ方は色々あります。自分なりの「関連グッズ」で、『王様のトリック』の世界をさらに深掘りしてみてください!)
まとめ:評価と総括 ★★★☆☆ (3/5)
『王様のトリック』は、「犯人は二人」という型破りな設定で読者を翻弄するクローズドサークル・ミステリーです。雪山の館という王道の舞台に新風を吹き込んだ意欲作であり、前半のスリルは抜群。反面、ミステリとしての詰めの甘さや後味の苦みもあり、万人に絶賛される作品ではないかもしれません。筆者としての評価は★3つとしましたが、これは光る部分と惜しい部分が拮抗している印象からです。
本作の位置づけを考えると、従来の本格ミステリーとは一線を画したエンターテインメント寄りのサスペンスと言えるでしょう。大胆なアイデアで勝負し、読者に新鮮な体験をさせてくれる一方、論理の緻密さよりは心理戦のスリルを優先した作品です。そういう意味では「トリックの王様」というより「疑心暗鬼ゲームの王様」といった趣があります。個人的には、発想勝ちのミステリーとして楽しみつつも「もう少し驚かせてほしかった!」という欲も出たのが正直なところです。
しかしながら、この作品が投げかけるテーマや独特の読後感は、読み物として確かなインパクトを残します。何より、読んだ後に「あの展開はどうだったんだろう?」と考察を巡らせたり、他の人の感想を読み漁ったりしたくなる点で、記憶に残る作品であることは間違いありません。ミステリー小説には、読者それぞれの感じ方で評価が変わる作品が時々現れますが、本作もまさにその一つでしょう。
最後に、この記事を通じて少しでも『王様のトリック』の魅力と課題をお伝えできていたら幸いです。奇抜なトリックに挑戦した吉村達也さんのチャレンジ精神に拍手を送りつつ、**あなたなら5人の中の誰を信じる?**という問いを残して締めくくりたいと思います。ぜひ本作を読んで、あなた自身の答えを見つけてみてください。そして感じたことを誰かと語り合えば、きっとミステリーの世界がもっと楽しくなるはずです。皆さんの感想や考察もぜひ聞かせてくださいね!
以上、最後までお読みいただきありがとうございました。