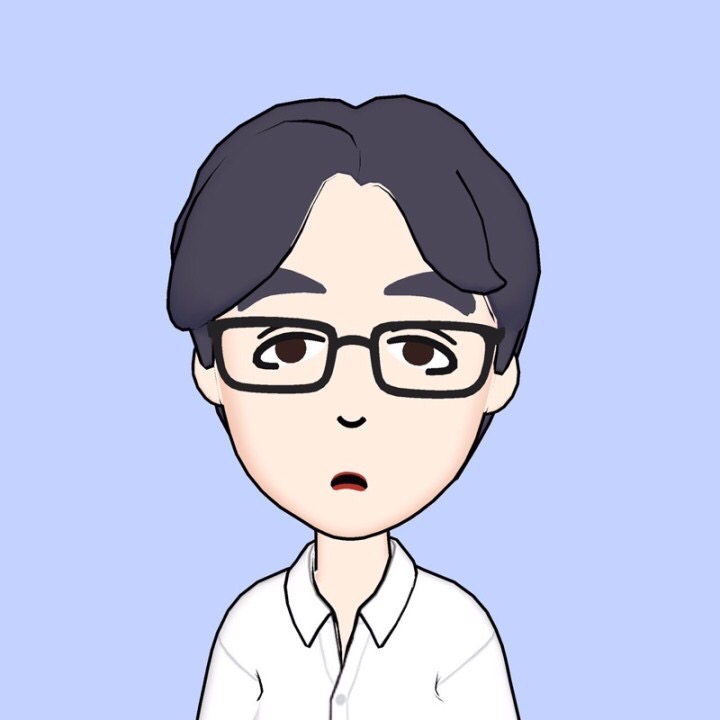水族館という日常の中で突如起きた密室殺人――しかも容疑者11人全員に完璧なアリバイがあるという前代未聞のシチュエーションが、本作『水族館の殺人』最大の魅力です。高校生たちが見学中の水族館で目撃したショッキングな事件、そして緻密に仕組まれたトリックに、読者である私も終始ハラハラさせられました。巧妙なトリックと個性豊かなキャラクターが共鳴し合う物語で、読後には「なるほど!」と膝を打つ爽快感が味わえることでしょう。この記事では、ネタバレを極力避けながら本作のあらすじや見どころを紹介し、さらに感想・考察で青崎有吾さんの真骨頂に迫ります。ミステリ好きならぜひチェックしたい話題作、その魅力をたっぷりお届けします。
著者紹介:青崎有吾とは
青崎有吾(あおさき ゆうご)さんは1991年生まれ、神奈川県横浜市出身の推理作家です。明治大学在学中の2012年、わずか20歳で長編デビュー作『体育館の殺人』にて第22回鮎川哲也賞を受賞し、本格ミステリ界に鮮烈なデビューを飾りました。以降も本格ミステリ大賞や日本推理作家協会賞の候補になるなど、若手エースとして精力的に活躍しています。代表作にはデビュー作のほか、『図書館の殺人』や連作短編集『ノッキンオン・ロックドドア』などがあり、“平成のエラリー・クイーン”の異名をとる論理派の新鋭です。
青崎作品の魅力は ずば抜けた論理性 と ポップな作風 の両立にあります。彼の推理はエラリー・クイーンを彷彿とさせるほど徹底的に論理的で、「何が起き、どう考えているか」が非常に筋道立てて分かりやすく書かれているのが特徴です。一方で物語の雰囲気はとても明るくコミカル。重大事件が起きているにもかかわらず、ユニークな登場人物たちの掛け合いが作品全体を軽やかに彩り、ページをめくる手が止まらないエンタメ性があります。つまり本格的な謎解きの緻密さと、ライトノベルのように親しみやすいキャラクター描写を兼ね備えており、それが青崎さんの真骨頂と言えるでしょう。実際「若き現代日本人が書いているので感情移入しやすく、はるかに読みやすい」という声もあり、本格ミステリ初心者から上級者まで幅広く楽しめる作風です。
本作『水族館の殺人』は、デビュー作に続く「裏染天馬シリーズ」第2弾にあたります。シリーズ各作品のタイトルには『体育館』『水族館』『図書館』といずれも「館」が付きますが、一見すると綾辻行人さんの〈館シリーズ〉を思わせつつ中身は全くの別物で、安定の本格ミステリ路線を貫いています。青崎さんはこのシリーズで毎回ユニークな舞台装置と驚きのトリックを用意し、若き名探偵・裏染天馬の活躍を描いてきました。本作でも作者ならではの論理トリックが存分に発揮されており、「平成のエラリー・クイーン」の異名に違わぬ巧みな謎解きが楽しめます。
登場人物紹介
主要な登場人物を、フルネーム(敬称略)で簡単にご紹介します。本作のドラマを彩る魅力的なメンバーたちにも注目です。
- 裏染 天馬(うらぞめ てんま) – 風ヶ丘高校の2年生男子。校内の百人一首研究会の部室に無断で住み着くほどマイペースなダメ人間で、アニメや漫画が大好きなオタク気質。細身で長い前髪に眠たげな目元という風貌ながら、その自由奔放な性格とは裏腹に天才的な推理力を持つ名探偵です。事件が起こると警察から“非常呼集”されるほど信頼されており、その卓越した論理思考で難事件の解決に大きく貢献します。
- 袴田 柚乃(はかまだ ゆの) – 風ヶ丘高校1年生の女子。セミロングの黒髪に幼さの残る顔立ちで、一見文学少女風ですが実は卓球部に所属する活発なスポーツ少女です。刑事である兄・袴田優作の影響もあってか、ひょんなことから裏染と共に事件捜査に関わることになります。天馬に振り回されつつも鋭いツッコミ役として活躍し、物語に明るいムードを添えるヒロイン的存在です。
- 向坂 香織(さきさか かおり) – 風ヶ丘高校2年生。天馬の幼なじみにして新聞部の部長を務める才女です。学年中ほとんどの生徒と顔見知りというほど社交的でパワフルな性格で、オタクな天馬ともアニメの趣味を対等に語り合える懐の深さがあります。普段はエネルギッシュに周囲を引っ張るまとめ役ですが、物語終盤では普段と違う表情を見せるシーンもあり、そのギャップにグッと心を掴まれます。
- 袴田 優作(はかまだ ゆうさく) – 横浜市警の刑事で、柚乃の兄。階級は警部。前作『体育館の殺人』で裏染天馬の推理力を目の当たりにしたことから、今作の水族館事件でも「高校生探偵」である天馬の力に期待し、捜査協力を要請します。警察内部では異例の決断ながら、自身も有能な刑事として天馬たちをバックアップし、真相解明に挑みます。
- 雨宮(あまみや) – 丸美水族館の飼育員の男性。本作の事件被害者であり、新聞部メンバーが取材中にサメの水槽で事故に遭ってしまいます。真面目で実直そうな人物でしたが、その死には不可解な点が多く、裏染天馬たちは彼の足取りや人間関係を手がかりに事件の背景を探っていくことになります。
この他にも、水族館職員や新聞部員をはじめ事件に関わる人物が多数登場します。容疑者に至っては総勢11名にも上り、それぞれに異なる個性や事情を抱えています。キャラクターの数は多いですが、その分「この中に犯人がいる」という推理ゲーム的な面白さが味わえるのも本作の特徴です。
あらすじ
夏休み真っ只中の8月4日。風ヶ丘高校新聞部のメンバーたちは、地域の穴場スポットとして評判の丸美水族館へ取材に訪れていました。館長に案内されながら館内を見学していた彼らでしたが、その最中に衝撃的な光景を目撃してしまいます。なんと観客で賑わう大水槽の前で、サメが男性飼育員に噛みついている現場に出くわしてしまったのです。後に被害者は水槽に落下した雨宮飼育員と判明。あまりに大胆かつ悲惨な事件に場内は騒然となり、新聞部員たちも急遽目撃者として事情聴取を受けることになります。
駆けつけた警察は当初、事故か怪奇な動物事故の可能性も疑いましたが、現場の状況から人為的な殺人事件と断定します。雨宮がサメに襲われたのはB棟にあるサメ水槽のバックヤードで、犯行当時(午前10時7分)そのエリアにいた人間は水族館職員を中心に全部で11人いました。ところが事情聴取と監視カメラ映像の分析により、その11人全員に犯行時刻の確固たるアリバイがあることが判明します。これには捜査陣も頭を抱え、事件は開始早々暗礁に乗り上げてしまいました。
そこで白羽の矢が立ったのが、風ヶ丘高校の裏染天馬です。たまたま夏休み中も学校に入り浸っていた天馬は、警部(柚乃の兄・袴田刑事)の要請で急遽捜査に参加することになります。天馬はマイペースな言動で警察を唖然とさせつつも、現場へ向かう車中で早くも容疑者を絞り込むヒントを掴んでみせました。一行が水族館に到着してからは、天馬・柚乃と警察の合同チームによる本格的な推理がスタートします。現場に残されたわずかな物的証拠(濡れたモップやバケツ、紙片、血痕、足跡、腕時計など)を徹底的に洗い出し、それらの意味を論理的に突き詰めていくことで、天馬は少しずつ「不可能に見えた殺人」の真相に迫っていきます。
物語中盤では、まず“全員アリバイ”のトリックが見抜かれます。天馬は現場の大水槽キャットウォークで発見した濡れたトイレットペーパーの塊に注目し、そこから着想を得てある仮説を立てました。それは、雨宮飼育員が人為的な細工によって時間差で水槽に転落させられた可能性です。具体的には、柵の扉と支柱の間にトイレットペーパーを巻き付け画鋲で固定し、雨宮を扉にもたれかからせておく仕掛けでした。上方の古い配管から滴る水が徐々に紙を濡らして脆くし、限界に達すると紙が切れて雨宮の体が支えを失い水槽へ真後ろに落下する――犯人はこの水滴タイマーを利用し、自分が現場を離れた後で事故が起きるよう仕組んだのです。結果、目撃された10時7分の落下時刻には犯人も含め誰も手を下しておらず、全員にアリバイが成立したように見えていたのでした。このトリックが明らかになることでアリバイの意味は崩れ、改めて11人全員が容疑者として振り出しに戻ります。同時に、「こんな回りくどい手を使う以上、犯人は単独犯で共犯者はいない」とも推理され、捜査の焦点は一人の真犯人を炙り出す方向へ絞り込まれます。
終盤、裏染天馬は推理の糸を一気に繋げていき、ついに真犯人を名指しする決定的な論理を組み立てます。11人の中から導かれた意外な犯人、そして「なぜ犯人はこんな大胆な犯行に及んだのか」という動機の謎にも二段構えの真相が隠されていました。物語ラストでは、事件の全容が明かされるとともに犯人の意外な背景に読者は驚かされ、同時にどこか切なさすら感じる結末となっています。犯人逮捕後、日常へ戻っていく天馬たち高校生の姿にほっと胸を撫で下ろしつつ、本作のミステリーは幕を閉じます。
感想
まず率直な感想として、想像以上に緻密で手応えのある本格ミステリでした。舞台が水族館ということで最初は「サメに襲われるなんて荒唐無稽では?」と思いきや、読み進めるとその舞台設定が巧みにトリックに活かされていることに感心させられます。サメの大水槽という非日常的なシチュエーション自体が強烈なインパクトを与えますし、そこで展開される謎解きは極めてロジカルで筋が通っており、「なるほど、そう来たか!」と唸る場面が多々ありました。特に全員にアリバイがあった理由が判明するシーンでは、何気ない小道具から推理を積み上げていく丁寧さに思わず膝を打ち、伏線回収の鮮やかさに脳汁がドバドバ出るような快感を味わいました。
登場人物たちのキャラクターも非常に魅力的で、本格ミステリでありながらキャラ小説としても楽しめる作品だと感じました。主人公の裏染天馬は「ダメ人間」ぶりが突き抜けていてユーモラスですし、柚乃との漫才のような掛け合いは笑えるポイントも多いです。序盤から主要キャラたちがワイワイ騒いで物語に引き込んでくれるので、シリアスな殺人事件を扱っていても全体の雰囲気が暗くなりすぎず読みやすかったです。青崎さんの作品らしくコミカルな会話がテンポ良く挟まれるおかげで、重厚な推理パートとのバランスがちょうど良い塩梅でした。例えば天馬が柚乃のことをいつまでも「袴田妹」呼ばわりして怒らせるシーンや、香織が天馬の趣味に乗っかって暴走するシーンなど、思わずクスっとする青春ドラマ的な描写もあり、読者として登場人物に愛着が湧きました。
印象的だった点として、謎解きの二段構え構成が挙げられます。本作では「誰が」「どうやって」という犯人当て・トリック当てだけでなく、「なぜそんなことをしたのか」という動機の謎にも大きなどんでん返しが用意されていました。犯人を特定した後にさらに動機面で意外性のある真相が明かされる展開には驚かされましたし、単なるパズルの解答に留まらない物語の深みを感じました。終盤で明かされる犯人の心理や背景には思わず「そうだったのか…」と唸ると同時に少し切なさも覚え、ミステリとしてのカタルシスと人間ドラマの余韻の両方を味わえたように思います。
一方、気になった点がないわけではありません。まず登場人物の多さにはやはり圧倒されました。容疑者11人に新聞部メンバー、さらには柚乃の家族や天馬の妹(!)まで次々と舞台に上がってくるので、人間関係を把握するのに少し神経を使います。もっとも、これについては本格ミステリ好きであれば「容疑者名簿が多いほど燃える」という方もいるでしょうし、実際私も読み終わってみれば必要な人物はきちんと印象に残ったので大きなマイナスではありませんでした。しかし人によっては「登場人物が多すぎて整理が大変」と感じるかもしれません。
また、トリックのためとはいえ偶然やご都合主義に思える部分も若干ありました。例えば犯行にトイレットペーパーを使う発想は斬新ですが、そのためにわざわざそんな危険で不確実な手を選ぶ必要があったのか?と考えると、動機面でもっと安全な方法もあったのでは…と思ってしまった部分もあります(もっとも本格ミステリでは「そこを言っちゃ野暮」という部分かもしれませんが)。実際、一部の読者からは「動機に納得できない」「いくらでも他に方法があるのでは」という声もありました。物語序盤の卓球大会のエピソードが本筋に絡まなかった点も、人によっては肩透かしに感じるかもしれません。私はキャラ描写として楽しめましたが、「結局事件に関係ないの!?」と拍子抜けした部分ではありました。
そして好き嫌いが分かれそうなのが、裏染天馬という探偵キャラのノリです。軽口を叩いては煙に巻くその言動はユニークで私は面白いと感じましたが、シリアスな推理シーンでも飄々としているので「探偵役がふざけすぎ」「軽薄に感じる」という受け取り方をする人もいるかもしれません。実際に「探偵役のキャラがどうも気に入らない」という読者感想も見られました。このあたりは本作の作風として割り切れるかどうかで評価が変わりそうです。ただ、裏染天馬のキャラクター性は本シリーズの大きな個性であり魅力でもあるので、ここがハマれば他にはない面白さを感じられるでしょう。
総じて、『水族館の殺人』は本格ミステリとしての緻密さとキャラクター小説としての面白さを両立させた秀作だと感じました。良い点・気になる点はありましたが、個人的にはそれらをひっくるめても大満足の一冊です。特に謎解き重視の読者にはたまらない作品ですし、逆に普段本格を読まない人でもキャラに親しめる分読みやすいと思います。読み終わった後には登場人物たちが愛おしくなり、シリーズの他の作品も手に取ってみたくなる、そんな魅力のある小説でした。
考察・解説
(※この章では物語の核心に触れるネタバレを含みます。未読の方はご注意ください。)
伏線とトリックの妙について、さらに深掘りしてみましょう。本作最大の仕掛けである「全員にアリバイがある密室殺人」は、実のところ時間差トリックによって成り立っていました。裏染天馬が見抜いたように、犯人は現場にトイレットペーパーと水滴を使った簡易な装置を仕掛け、ターゲットである雨宮を計画的に水槽へ転落させました。この発想自体は奇想天外ですが、現場の状況(古い配管からの水漏れや濡れた紙片の存在)から論理的に導き出せるもので、読者も注意深く読めば見破れる絶妙なラインのトリックになっています。実際、何気ない情景描写の中にこのトリックを示唆するヒントが紛れ込んでおり、一度真相を知ってから振り返ると「あの描写はそういう意味だったのか!」と気付かされる巧妙さでした。青崎有吾さんは伏線の配置が非常に緻密で、読者が「これ重要かも?」と目を付けるような箇所にわざとフェイクのヒントを置き、本当に重要な手掛かりは背景にそっと忍ばせるというテクニックがお見事です。私自身、途中で怪しいと思った点に付箋を貼りながら読んでいましたが、見事にミスリードされました…。こうした伏線と叙述の巧みさが、本格ミステリファンにはたまらない醍醐味になっていると思います。
「謎の共鳴」という副題にもあるように、本作では複数の謎が共振し合うような構造になっています。具体的には、まず表層的な謎としての「不可能状況のトリック」があり、次に深層的な謎として「犯人の動機」があります。この二つの謎は密接に絡み合っていて、トリックが解明されると同時に「では一体なぜそんな手の込んだ真似を?」という新たな疑問が浮上する仕組みです。犯人はなぜ観客の目前であえてサメに死体を喰わせるという劇場型の犯行に及んだのか? その“Why(動機)の二段オチ”が最後に待っており、読者への大きなサプライズになっています。この二段構えの真相解明は、本格ミステリではエラリー・クイーンなどが得意とした手法でもありますが、青崎さんも負けず劣らず鮮やかにやってのけました。犯人の動機について詳しくは伏せますが、「ある目的」のためにあえて目立つ方法で殺人を演出していたことが明かされ、その意外性と論理的整合性には脱帽しました。「盲点は常に一番大きなところにある」というミステリのセオリーを体現するような仕掛けで、まさに目の前にありながら見抜けなかった真実に気付かされたとき、鳥肌が立つような興奮を覚えました。
トリック面では他にも、水族館という舞台ならではの小道具が数多く活かされています。例えば黄色いモップや血の付いたタオル、バケツの水、水槽の足跡など、一見ただの清掃用具や事故の痕跡に過ぎないものが、実は犯人を指し示す重要なピースとなっていました。タイトルに「水族館の殺人」と銘打ちながら、副題に "The Yellow Mop Mystery" とあるのも、この黄色いモップが事件解決のカギを握っていることへの示唆でしょう(実際、本作ではモップに関する論理が謎解きの山場の一つになっています)。青崎さんはこうした手掛かりの配置と回収に非常に気を配っており、細かいディテールまで論理の網を張り巡らせています。そのため、読み飛ばした些細な描写が後になって大きな意味を持って浮かび上がることも多く、注意深い読者ほど「してやられた!」と快感を味わえる作りになっています。
シリーズものとして見た場合、本作では前作『体育館の殺人』から引き継いだキャラクターのドラマも深まっています。例えば新キャラクターとして裏染天馬の妹(忍切*蝶子)が登場し、天馬に勝るとも劣らないクセ者ぶりで物語を引っ掻き回しました。彼女と新聞部長・佐川(香織)との火花散る掛け合いは脇筋ながら読み応えがあり、「強敵と書いて友と読む」的な盛り上がりを見せています。もっとも、このキャラに関しては「物語とどう絡むか期待したがそのまま出番が終わって残念」と感じた声もあり、シリーズ次回作での活躍に期待が持たれます。柚乃と天馬の関係性も微妙に進展(?)が見られ、天馬の部屋に柚乃が入り浸る仲になっていたりと、青春小説的な要素もちらほら散りばめられていました。こういったキャラクター同士の関係の機微も、本格推理の合間に描かれることで物語に奥行きを与えています。
他作品との比較で言えば、青崎有吾さんの作風はやはりエラリー・クイーン直系のロジック重視と言えます。実際に本作を読んで「まさにクイーンだ」と感じた読者も多く、たくさんの手掛かりを少しずつ積み上げて最後に犯人を指摘する流れは「クイーンそのもの」と評されています。同時にキャラクターの魅力や現代的な語り口によって読みやすさが向上している点が、青崎作品のオリジナリティでしょう。個人的には、有栖川有栖さんの学生アリスシリーズなどがお好きな方にはこの裏染天馬シリーズも刺さるのではないかと感じました(事実、「有栖川有栖より好みかも」との声もありました)。論理の精緻さで群を抜いていると同時に、キャラ造形や会話劇はアニメ映えしそうなほどポップという両面を持ち合わせており、まさに平成生まれの新本格というべき作品世界が確立されていると思います。
最後に、本作の読者への挑戦についても触れておきます。文庫版ではなんと物語中に明確に「読者への挑戦状」が挿入されており、犯人やトリックの解明パートの直前で「ここまでで推理できるか挑んでみてほしい」というメッセージが提示されます。これは往年の名探偵小説へのオマージュであり、同時に青崎さんが読者と対等にゲームを戦う姿勢の表れでしょう。私も挑戦状のページで一旦本を閉じ、自分なりに犯人とトリックを推理してみましたが…結果は見事に外れました(笑)。しかし、それでも種明かしを読んだ後には悔しさよりも「やられた!」という清々しい敗北感と満足感が残りました。論理を尽くして読者を惑わせ、最後には納得させるという本格ミステリの王道を、本作はしっかりと踏襲しているのです。
読者の反応
本作『水族館の殺人』に寄せられたSNSやレビューサイトでの読者の反応を、ポジティブ・ネガティブそれぞれ5件ずつピックアップしてみました。
読者の反応は概ね高評価ながら賛否の分かれる点もあるようです。特に「トリックの論理性」と「キャラクターの魅力」は多くの読者が称賛しており、「作者は本物」「平成のクイーンの名に相応しい」といった声が目立ちました。一方で、登場人物の多さや動機設定の妙に関して「消化不良」と感じる人もおり、作品のポップなノリや探偵役のキャラに合う合わないで評価が分かれる面もあるようです。しかし総じて、本格ミステリファンからは「論理の精緻さが素晴らしい」と支持されており、シリーズものとしてキャラクターへの愛着も深まっていることから、続編への期待も含め高い評価を得ている印象です。
ポジティブな反応(称賛) 🟢
- 「舞台を体育館から水族館に移しての裏染天馬シリーズ第2弾。面白かった!青崎氏は本物だ!キャラクターもより魅力的に!」x.com(シリーズファンの興奮が伝わる感想)
- 「二作目でこの水準なのはこの作者が本物な証拠だと思う。論理の緻密さで群を抜いている。」(著者の実力とロジックの凄さを高評価)
- 「たくさん登場人物が出てきて、ほとんど完全犯罪みたいで、手がかりは小さなところから少しずつ論理を積み上げて犯人指摘に至るところはクイーンそのものといった感じ。さらに現代の若い日本人が書いているので感情移入しやすく、はるかに読みやすい。」(古典的な論理と現代的な読みやすさの融合を評価)
- 「伏線描写が緻密。残念ながら私には推理できませんでした…。これは重要なのでは?と思った所に付せん貼ってたけど全然重要じゃなかった。推理パートで該当箇所を振り返りながら読み進めていくとめちゃくちゃ脳汁出ます。」(伏線回収の快感に言及した感想)
- 「動機はちょっと気になりますが、ヒロイン役との関係性がラノベ風で面白かったです。」(トリックだけでなくキャラの掛け合いも楽しめたという声)
ネガティブな反応(批評) 🔴
- 「殺人の方は、手掛かりがやたらチマチマしている。容疑者が属性だけ貼り付けたロボットみたいで、11人は流石に多過ぎ。」(手掛かりが細かすぎ、登場人物が多すぎるとの指摘)
- 「動機には全く納得できないし、違った方法で解決できたはず。」(犯行動機への疑問。回りくどい方法に必然性が感じられないという批判)
- 「序盤の卓球大会の描写は何だったの?...全く関係ないなんて酷すぎる。」(物語序盤のエピソードが本筋に絡まない点への不満)
- 「探偵役のキャラクターも、変なノリだしどうも気に入らない。」(裏染天馬のキャラが合わず、受け入れられなかったという意見)
- 「解決編を読んでもいまいちピンときませんでした…。例えると、ウィキペディアの数学の定理の項目を見ているときの理解できない感じと同じでした。」(論理が難解すぎて理解が追いつかず楽しめなかったという声)
次回への期待
『水族館の殺人』を読み終えたら、ぜひシリーズ次作にも手を伸ばしてみてください。裏染天馬シリーズはこの後、舞台を図書館に移した長編第3作『図書館の殺人』へと続いていきます。次はどんな「館」でどんなトリックが待ち受けているのか、天馬や柚乃たちの活躍を追いかけずにはいられません。実際、シリーズを通じて謎もスケールアップしており、作者は前作以上に緻密な論理を組み上げてみせています。本作で張られた伏線やキャラ関係も、次作以降でさらに掘り下げられる可能性があります。例えば天馬の過去や家族の謎、柚乃との関係の進展など、シリーズを読み進めれば裏染天馬という探偵像により深く迫れることでしょう。
また青崎有吾さんはこのシリーズ以外にも注目作を発表しています。中でも『ノッキンオン・ロックドドア』シリーズは様々な難事件(いわゆる“不可能犯罪”)に2人組の探偵が挑む連作短編集で、こちらはテレビドラマ化もされ話題となりました。さらに異色作として『アンデッドガール・マーダーファルス』という妖怪×ミステリのシリーズもあり、こちらはアニメ化されて新たなファンを獲得しています。青崎作品にハマった方は、ぜひこれら他作品にも触れてみてください。本格ミステリの伝統と現代的エンタメが融合した青崎ワールドは一度体験すると病みつきになるはずで、きっと次から次へと読みたくなってしまうことでしょう。
そして何と言っても、裏染天馬シリーズの今後の展開にも大いに期待したいところです。現在シリーズ最新作として短編『風ヶ丘五十円玉祭りの謎』や長編予定の『地雷グリコ』などのタイトルが示唆されており、裏染兄妹が挑む新たな事件が描かれるのではとファンの注目を集めています。天馬たちが次にどんな舞台で難事件に挑むのか、シリーズファンとして待ち遠しい限りです。さらに、その独特のキャラクターと論理のバトルは映像化しても映えること間違いなしなので、いつかドラマやアニメで裏染天馬が活躍する姿も見てみたいですね(作者自身「これほどアニメ化に向いている小説もない」と語っています)。シリーズが続けば続くほど盛り上がること必至の裏染天馬ワールド、ぜひ皆さんも追いかけてみてください!
関連グッズ紹介
最後に、『水族館の殺人』に関連する書籍やグッズをいくつかご紹介します。
- 書籍『水族館の殺人』 – 東京創元社より単行本と創元推理文庫で刊行中。文庫版(創元推理文庫443-12)はイラストレーター田中寛崇さんによるポップなカバーイラストが目印で、巻末には解説も収録されています。電子書籍(Kindle他)でも配信されており、気軽に入手可能です。
- 裏染天馬シリーズ既刊本 – シリーズ第1作『体育館の殺人』、第3作『図書館の殺人』(ともに創元推理文庫)が刊行中です。シリーズを順番通り読むことでキャラクター関係や過去の事件への言及もより楽しめます。まずは『体育館の殺人』から読み始め、本作『水族館』、そして『図書館』へと進めば完璧です。
- オーディオブック版 – 朗読:浅井晴美さんによる『水族館の殺人』のオーディオブックが配信されています。総朗読時間約11時間40分にわたり物語を耳で堪能できるので、通学通勤中や家事の合間など“ながら読書”にもぴったりです。臨場感ある語りでキャラクターの掛け合いが楽しめると好評です。
- コミカライズ情報 – 2025年現在、シリーズ第1作『体育館の殺人』がコミカライズ連載中です(マンガアプリ等にて連載)。裏染天馬や柚乃たちが漫画でどのように描かれるか要注目です。今後『水族館の殺人』や『図書館の殺人』のコミカライズ展開にも期待が寄せられています。
- その他グッズ – 東京創元社のオンラインストア等では、本シリーズのカバーイラストを使用したブックカバーやポストカードが制作されることもあります(期間限定キャンペーンなど)。また、本作の舞台・水族館にちなんでサメのキーホルダーやマスコットを購入し、読後の余韻に浸るファンもいるようです(公式グッズではありませんがちょっとした楽しみとして…)。お気に入りのアイテムとともに作品世界を味わってみるのも一興でしょう。
まとめ
青崎有吾さんの『水族館の殺人』は、密室状態の水族館で起きた奇想天外な事件を、高校生探偵が論理の力で解き明かす痛快ミステリーです。巧緻なトリックと緻密な伏線、そして個性豊かなキャラクターの掛け合いが見事に融合し、ページをめくる手が止まらないエンターテインメントに仕上がっています。読み終えた後には、「本格ミステリって面白い!」と心から感じられることでしょう。
評価:★★★★☆(4/5)
総合的に見て、本作は本格ミステリとして非常に完成度が高く満足度の高い一冊でした。多少の荒唐無稽さや好みの分かれる部分はあるものの、それを補って余りある論理の妙と物語の熱量があります。若き名探偵・裏染天馬の活躍は痛快で、彼を取り巻く仲間たちとのやり取りも微笑ましく、最後まで飽きさせません。ミステリ初心者から玄人まで幅広くお薦めできる良作です。
青崎有吾さんは本シリーズ以外でも次々と話題作を発表し、ミステリ界を盛り上げています。今後の裏染天馬シリーズの展開や、他作品でのさらなる挑戦にも大いに期待したいですね。ぜひ皆さんもこの挑戦的な謎に挑み、解き明かす快感を味わってみてください。そして気に入ったなら、シリーズの続編や青崎作品の世界へどんどん踏み込んでみましょう。きっと次なる“館”で、また新たな驚きと発見があなたを待っています!