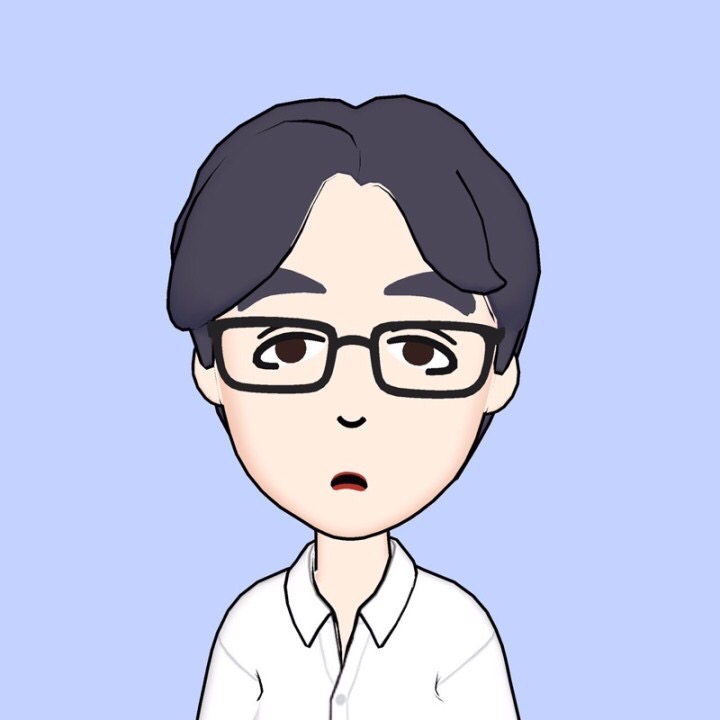落語×少年ジャンプという異色の組み合わせで話題の漫画『あかね噺』。第5巻では、主人公・朱音が落語界の“伝統の壁”に真正面から挑みます。前巻までで培われた実力を武器に、先輩噺家への痛快なお返し劇もあり、読後には思わず拍手喝采したくなる展開でした。今回はそんな『あかね噺』第5巻の見どころや深掘り考察を、ネタバレを極力控えつつご紹介します。落語に詳しくなくても楽しめる青春ストーリーの魅力を、親しみやすい視点で語っていきますので、「次に何を読もう?」と迷っている方はぜひチェックしてみてください!
著者紹介
本作の原作を手掛けるのは末永裕樹さん、作画を担当するのは馬上鷹将さんです。末永裕樹さんは熊本県出身の漫画原作者で、本作が週刊少年ジャンプでの連載デビュー作。以前には漫才を題材にした読み切りを発表しており、伝統芸能や表現者の世界を題材にする作風が光ります。好きな作品にジャズ漫画『BLUE GIANT』やバスケ漫画『SLAM DUNK』を挙げており、その影響か『あかね噺』にも情熱的な青春ドラマのエッセンスが感じられます。馬上鷹将さんも本作で連載デビュー。躍動感ある描線と豊かな表情描写で、音のない漫画でありながら落語の熱気や笑いを読者に伝える実力派の漫画家です。二人のタッグにより、生き生きとしたキャラクター達と臨場感あふれる高座シーンが魅力の作品となっています。
登場人物紹介
- 桜咲 朱音(おうさき あかね) – 本作の主人公。高校生にして落語家の道を歩む前座噺家です。父の無念を晴らすため真打(しんうち)昇進を目指し、師匠仕込みの確かな実力と負けん気の強さで奮闘中。この第5巻では、自分に意地悪をしてきた先輩に機転と話芸でやり返す痛快シーンがあり、持ち前の度胸を見せてくれます。一方で落語家社会の厳しさにも直面し、新たな課題と向き合うことに…。読者目線でも応援したくなるまっすぐなヒロインです。
- 阿良川 志ぐま(あらかわ しぐま) – 朱音の師匠であり、阿良川一門の落語家。寡黙ながら朱音に6年間もの基礎修行を積ませた指導力の持ち主。革新的な落語を良しとするタイプで、弟子の朱音にも型にとらわれない才能を感じています。第5巻では朱音の今後を案じつつ、他の師匠からネタを教わることを許可する懐の深さも見せます。過去には朱音の父とも因縁がありそうなベテランで、渋い存在感が光ります。
- 今昔庵 りゑん(こんじゃくあん りえん) – 二つ目(ふたつめ)の落語家。いわゆる「新人潰し」の異名を持ち、寄席で前座の朱音に意地悪を吹っかけてきた張本人です。プライドが高く、立場を笠に着て横暴な振る舞いをするため周囲からも煙たがられがち。本巻では朱音との間で騒動を起こし、彼女に恥をかかされる展開に。いわば因縁の相手として物語を動かす役回りです。
- 柏家 禄郎(かしわや ろくろう) – 将来を嘱望される若手の二つ目。黒髪くせ毛の好青年で、落語連盟幹部・柏家三禄(みろく)を師匠に持つエリートです。後輩思いの性格から下積みの前座たちにも優しく慕われています。落語の型は“言葉による音楽”と称され、軽妙なリズムで客席を魅了する芸風が持ち味。朱音とりゑんのいざこざでは仲裁に入り、場を収めるなど人望の厚さを見せました。物語後半では朱音に重要な機会を与えるキーパーソンとして登場します。
- 蘭彩歌 うらら(らんさいか うらら) – 落語界を代表する真打の一人で、女性落語家のパイオニア的存在。常に和服姿のクールビューティーで低姿勢ながら、その実力は折り紙付きです。色気と品格を備えた「廓噺(くるわばなし)」を十八番とし、伝統芸能の粋を極めた大看板。第5巻の終盤で初登場し、朱音にとって憧れのロールモデルとなり得る人物です。男性社会と言われる落語界で頂点に立つ彼女の言動は必見で、朱音に新たな刺激を与えてくれます。
この他、第5巻では朱音に噺を教える相談を受けた椿家 八正(つばきや はっしょう)というベテラン落語家も登場します。柔らかな語り口が持ち味の温厚な人物ですが、朱音が起こした騒動ゆえに弟子入りを断る厳しさを見せました。物語に深みを与える脇役として注目です。
あらすじ
前座修行中の朱音は、寄席小屋「弥栄亭」で雑用や前座高座に励む日々を送っています。そんな中、同じ寄席に出ていた二つ目・今昔庵りゑんから理不尽ないちゃもんをつけられてしまいます。りゑんは新人いびりで有名な噺家で、朱音に対し「出がらしのお茶を出しただろう」などと難癖をつけ、高座に上がる前から嫌がらせを仕掛けてきました。普段は温厚な朱音もこれには黙っていられません。
折しも寄席の席亭(主催者)が機転を利かせ、朱音をその日の開口一番(いわゆる一番手の前座)に指名します【※開口一番: 寄席で一番最初に上がる前座のこと】。高座に上がった朱音は、この場でりゑんに一矢報いることを決意。彼女が披露した演目は古典落語の「山号寺号(さんごうじごう)」。お寺の名前(山号と寺号)を題材にしたコミカルな噺で、朱音は持ち前のテンポの良い語り口で客席の笑いをしっかりと掴みます。序盤は「所詮前座」と興味なさげだった観客たちも、朱音の生き生きとした話芸に次第に引き込まれていきました。
極めつけは噺の中盤、朱音が即興で織り交ぜた一節です。りゑんが文句を言っていた「出がらしのお茶」をネタにして、まるで彼を茶化すかのようなアドリブを披露したのです。突然の機知に客席は大爆笑。【朱音:「へぇ、お茶にも二番煎じってのがございまして…」】痛烈な皮肉を交えつつも笑いに昇華した朱音の芸に、意地悪なりゑんも顔を真っ赤にするばかり。こうして前座ながら高座で先輩に“鼻を明かす”という前代未聞の勝利を収め、朱音は爽快な達成感を得ました。
しかし高座を降りた後、そのツケが回ってきます。プライドを傷つけられたりゑんは当然激怒し、「前座の分際で俺に恥をかかせたな」と朱音に詰め寄ります。朱音も負けずに「やられっぱなしでいる性分じゃないので」と涼しい顔で言い返し、一触即発のムードに…。その場は居合わせた柏家禄郎が間に入り、「まぁまぁ」と二人を宥めて大事には至りませんでした。しかし今回の件で「朱音が格上の先輩に歯向かい、しかもそれに落語という舞台を使った」という噂が業界内に知れ渡ってしまいます。師匠の阿良川志ぐまとしてはヒヤリとする出来事で、朱音自身も後になって事の重大さに気づくのでした。
寄席での騒動後、朱音には新たな課題が浮上します。それは持ちネタの少なさです。実は朱音がこれまで習得した前座噺(まえざばなし)はたった五席しかありませんでした。師匠・志ぐまが基礎を重視し敢えて演目を絞って教えていたためですが、前座として各席でやっていくにはネタが重複しないよう数多くの噺を身につける必要があります。今後も寄席に上がり続けるには、新しい噺を覚えなくてはなりません。志ぐまから直接教わる以外に他の師匠筋にも弟子入りしてネタを伝授してもらう――つまり他門の師匠に稽古をつけてもらうことが不可欠になったのです。
タイミングよく、朱音はベテラン真打の椿家八正にあいさつし、稽古をお願いしようと考えました。落語界では年長の師匠から演目を教えてもらうこと自体は珍しくありません。ところが八正は朱音の頼みを聞く前から「君が例の…高座で噂になっている子かい?」と渋い表情。そう、朱音がりゑん相手にやってしまった一件が業界に知れ渡っており、八正は「落語という神聖な場を私闘に使うとは感心しないね」と苦言を呈したのです。さらに「師匠の志ぐま君にもよろしく」と、朱音の申し出をやんわり断ってしまいました。朱音にとっては痛恨の事態です。自分の行いが原因で稽古を拒否され、噺を増やす道が閉ざされてしまいました。若さゆえの暴走だったのか…朱音は落語家としての自分の未熟さを思い知らされ、しょんぼり肩を落とします。
しかし、ここで終わらないのが朱音の奮闘譚です。彼女は落ち込むだけでなく、自ら反省し次のチャンスを探ります。そんな折、先日の騒動で仲裁に入ってくれた禄郎から声がかかりました。なんと柏家禄郎と椿家八正の二人会(ふたりかい)が開かれることになり、朱音もその高座で前座を務めないかというのです。禄郎は朱音の才能を買っており、師弟関係の垣根を超えてエールを送ってくれました。もちろん朱音はこのチャンスを逃しません。「ぜひやらせてください!」と即答します。ただし問題が一つ。肝心の演じる演目を新たに用意しなければなりません。八正からは断られましたが、別の師匠に教わる道が残されています。そこで白羽の矢が立ったのが、女性真打の蘭彩歌うららでした。禄郎の仲介もあり、朱音はうらら師匠に直接弟子入りして噺を教わるという大役に挑むことになります。
朱音が稽古を乞うた演目は、うららが得意とする**「廓噺(くるわばなし)」**でした。遊女や花街を題材にした色っぽい古典落語で、女性が演じるのは難しいとされるジャンルです。うらら師匠は快く朱音を迎え入れ、この廓噺「お茶汲み」という一席を彼女に伝授することに。鬼気迫るような美しい語り口で知られるうららの芸を、朱音はどこまで吸収できるのか──。伝統の大看板から直接お墨付きをもらった形の朱音ですが、その分プレッシャーも相当です。物語は、朱音が新たな師匠・うららとの稽古に臨もうとする場面で幕を閉じます。笑いで逆境を切り抜けた彼女が、次にぶつかった“落語の壁”をどう乗り越えるのか。続巻への期待が高まる終わり方でした。
感想
第5巻は序盤からスカッとする展開で、一読者として爽快感を味わいました!朱音が前座の身でありながら意地悪な先輩に機転で仕返しするシーンは、「よく言った!」と膝を打ちたくなる痛快さです。落語の演目中にさりげなく相手を揶揄するなんて、小悪魔的でいて痛烈。観客だけでなくこちらも思わずニヤリとしてしまいました。普段は礼儀正しい朱音が見せた反骨精神には、彼女の芯の強さを改めて感じます。
とはいえ、読み進めるにつれ「やりすぎちゃったかな…」とハラハラもしました。案の定、年長者たちからは「落語を私怨に使うとは何事だ」と叱られてしまう朱音。確かにプロの噺家としては軽率だったのかもしれません。先輩を笑いものにしてしまったら業界で浮いてしまうリスクもありますよね。このあたりの伝統と若さの衝突がリアルに描かれていて、「ただの勧善懲悪で終わらない」物語の深みを感じました。読んでいて胸がすく思いと同時に、その後の苦い展開で考えさせられる…感情をジェットコースターのように揺さぶられました。
新キャラクターの登場も熱かったです!特に終盤で姿を見せた蘭彩歌うらら師匠には痺れました。女性でありながら真打の大看板という存在感、登場シーンのオーラが凄いんです。朱音が委縮しちゃうくらいの圧倒的な雰囲気なのに、どこか優しげでもあって。「志ぐまくん」と自分の弟弟子(※志ぐま)を呼ぶくだけた一面も見せたりと、人間味も感じられるキャラクターですね。うららが高座で披露した妖艶な廓噺のワンシーンは、漫画のコマから色気が漂ってくるようでドキッとさせられました。演目の内容自体も気になりますし、朱音が彼女から何を学ぶのか今からワクワクします。
作画の面でも第5巻は見ごたえ十分でした。落語シーンでは観客の笑い声やどよめきがこちらに伝わってくるような迫力があります。朱音が高座で見せる表情や所作も細やかに描かれていて、まるで実際に噺を聞いているかのような臨場感!特に朱音がりゑんをからかう瞬間のイタズラっぽい笑みは、読んでいて「やるなぁ」と思わず唸りました。また合間に挟まれるオマケ漫画やオフショット的なコマでは、キャラクター達の素の姿が垣間見えてクスリと笑えます。シリアスな本編との緩急が絶妙で、何度でも読み返したくなる演出です。
全体として、第5巻は物語が大きく動いた重要な巻でした。朱音の快進撃と躓き、新たな出会いがぎゅっと詰まっていて、読後は「早く続きが読みたい!」という気持ちにさせられます。感情移入して一緒に笑ったり落ち込んだり、とても充実した読書体験でした。落語という渋いテーマを扱いながら、ここまで胸を熱くさせてくれるとは…やっぱり『あかね噺』は侮れません!
考察・解説
『あかね噺』第5巻では、「伝統VS革新」というテーマがひと際浮き彫りになっていたように感じます。朱音の大胆な行動は、古いしきたりに一石を投じるものであり、若い才能が閉鎖的な業界でどうもがくかという物語の核心が描かれました。落語の世界では、師匠から教わった「型」を大切に守る反面、常に観客を沸かせる創意工夫も求められます。朱音は師匠仕込みの型を持ちながら、自分なりの機転(アドリブ)で笑いを取ってみせました。この姿は伝統芸能の継承と革新のせめぎ合いを象徴しており、読者にも「新しさ」と「古き良きもの」のバランスについて考えさせます。実際に八正から咎められたように、落語家にとって高座は真剣勝負の場。私怨を持ち込むのはご法度ですが、朱音はそれを笑いに変えることで結果的にプロとして成立させてしまった。このあたりの是非は読み手によって解釈が分かれそうですが、だからこそ議論したくなる面白さがあります。
また、女性が活躍する落語界という点も興味深いテーマです。現実の落語の歴史では女性噺家は少数派でしたが、近年は徐々に増えてきています。作中のうらら師匠はまさに「ガラス天井を突き破った存在」として描かれており、朱音にとって明確なロールモデルでしょう。男性ばかりの寄席で女性がスターになる大変さは想像に難くありませんが、うららは実力でそれを成し遂げています。朱音もいずれはその域に…と夢が膨らみますね。二人の交流シーンは、単に師弟というだけでなく「落語界における女性同士の絆」のようなものも感じて胸が熱くなりました。ここに、父と娘の物語である『あかね噺』がもう一つ新しい視点(女性の視点)を得たようにも思えます。
落語の演目や用語の解説も巧みに盛り込まれていました。例えば「山号寺号」とは寺院の正式名称のことで、実在の小噺を踏まえています。さらに朱音が教わる「廓噺」は江戸時代の遊郭を舞台にした艶っぽい噺で、現実でも女性噺家が演じるのは難易度が高いと言われるジャンルです。それをあえて朱音に伝授するうらら師匠…これは朱音の才能を見込んでのことか、それとも何か試練を与えようとしているのか?深読みすると、うらら自身が歩んできた茨の道を朱音にも疑似体験させようとしているようにも捉えられます。落語という芸の伝承は、単にネタを覚えるだけでなく師匠の思想や覚悟までも受け継ぐことなのだと感じました。このように演目選び一つにも意味が込められているのは、本作の脚本の巧みさですね。
他作品との比較で言えば、『あかね噺』は演芸ものとしては異例の少年漫画ですが、その熱血ぶりはスポ根にも通じます。かつて少女漫画で演劇の世界を描いた『ガラスの仮面』や、ジャンプで芸能界を題材にした『アクタージュ』(未完)などを彷彿とさせる部分もあります。主人公が師匠から英才教育を受け成長していく様は、『スラムダンク』の湘北メンバーが基礎練習を叩き込まれて強くなっていく姿にも重なりました。実際、作中で朱音の修行をRPGのレベル上げに喩える描写もあり、古典芸能でありながら少年ジャンプらしい“バトルもの”の高揚感が味わえるのも面白い点です。「落語×バトル」というと奇抜ですが、読めば読むほど違和感なくハマってしまうのは作者たちの手腕ですね。
最後に、演出面で印象的だったのは緩急のつけ方です。シリアスな場面の後にはコミカルな小ネタが入り、読者をリラックスさせてくれる構成はまるで寄席の幕間のよう。第5巻では特に、朱音とうららの登場で作品初の“女子会”的なほのぼのシーンもあり、クスッと笑えて癒やされました。こうした細やかなサービス精神があるからこそ、シリアスな展開も重くなりすぎず読みやすいのでしょう。落語の「オチ」で一息つくように、漫画の随所に散りばめられた笑いが作品全体を引き締めています。
読者の反応
第5巻発売後、SNS上でも盛り上がりを見せました。以下に主なポジティブ/ネガティブな反応をまとめます。
ポジティブな反応(好評) 🟢
- 「朱音ちゃんの高座での逆襲、スカッとした!何度も読み返してニヤニヤしちゃう」
- 「うらら師匠カッコ良すぎ…女性キャラがこんなに魅力的な漫画は初めてかも!」
- 「落語のシーンで泣けるなんて思わなかった。観客の笑いと朱音の覚悟に胸アツ!」
- 「絵の迫力がすごい。実際に声が聞こえてきそうで鳥肌立った!」
- 「伝統芸能をテーマにここまでワクワクさせるなんて天才。アニメ化したら絶対観たい!」
ネガティブな反応(賛否両論・批判) 🔴
- 「前座が先輩にあそこまでするのはリアルじゃ有り得ない?ちょっとご都合主義に感じた」
- 「朱音に甘すぎる展開かも…。あれで干されるどころかチャンス掴むのは出来過ぎでは?」
- 「落語の専門用語が多くて少し難しかった。解説欲しいシーンもあったかな」
- 「話の展開が駆け足に感じた。禄郎やうらら登場までもう少しじっくり描いて欲しかった」
- 「りゑんの嫌がらせ描写が胸糞すぎて読んでて辛かった…もう少しソフトでも良いのに」
こうした声が上がっていましたが、全体的には好意的な反応が多数派でした。特に朱音の“笑いによる逆襲”シーンは「痛快すぎる!」と大好評で、Twitterでは「あかね噺」が一時トレンド入りするほど注目を集めました。一方で、一部には物語の都合の良さや展開の速さを指摘する意見も見られました。しかし「フィクションだからこその爽快感を楽しむべき」「専門用語は巻末やネットで補完できる」といった擁護の声もあり、議論も含めて盛り上がりを見せていたようです。総じて、第5巻は読者の心を動かし「早く続きが読みたい!」という熱いリアクションを生み出したエピソードと言えるでしょう。皆さんはどのシーンがお気に入りでしたか?ぜひ感想を聞かせてくださいね。
次回への期待
波乱含みだった第5巻のラストを受けて、次の第6巻への期待も高まります。最大の注目ポイントは何と言っても朱音が挑む廓噺の高座でしょう。うらら師匠直伝の艶やかな演目を、朱音が自分のものとしてどう演じ切るのか想像するだけでワクワクします。女性にとって難しいとされるジャンルだけに、成功すれば彼女自身の殻を破る大きな成長となるはずです。反対に失敗すれば落語家として致命的な評価を受けかねない大勝負でもあります。朱音はこのプレッシャーに打ち克ち、観客を唸らせることができるのか──今からドキドキが止まりません。
また、意地悪だったりゑんや八正師匠たち周囲の反応にも注目です。朱音が見事廓噺をやり遂げた暁には、彼女に冷たかった人々も評価を改めるのではないでしょうか。りゑんとの関係も、この先和解や再戦があるのか気になるところです。一度は衝突した先輩後輩が互いに認め合う日は来るのか…個人的には朱音とりゑんがいつか同じ高座で笑い合える関係になってほしいなと思っています。
さらに、朱音の師匠・志ぐまとうらら師匠の過去や関係性も深掘りされそうです。うららが志ぐまを「志ぐま君」と呼ぶシーンには思わずニヤリとしてしまいましたが、年齢的には彼女の方が上なのか、それともただのフランクな間柄なのか?このあたりの裏話も垣間見えるとファンとしては嬉しいですよね。朱音が二人の会話からプロの心得を学ぶ場面などもあるかもしれません。
第6巻以降では物語の舞台がさらに広がり、朱音の前座卒業や真打昇進試験といった大きなイベントも控えていそうです。父・志ん太の夢だった真打に朱音が近づくにつれ、師匠や仲間たちとの絆もより深まっていくでしょう。今回の試練を乗り越えた彼女なら、どんな困難も笑顔で乗り切ってくれるはず!引き続き朱音の成長物語から目が離せません。次巻での活躍に期待して、発売を心待ちにしたいと思います。
関連グッズ紹介
『あかね噺』の世界をもっと楽しみたい方へ、作品にちなんだグッズもいくつかご紹介します。まず、ジャンプ公式キャラクターズストアから発売されている**「あかね噺 トートバッグ」**は要チェックです。劇中で朱音が使う扇子や定紋をあしらったおしゃれなデザインで、普段使いにもピッタリと評判。荷物を持って全国を巡業する噺家気分が味わえるかも?
また、同ストアでは朱音やからし達キャラクターの名場面セリフがプリントされた**「コマステッカー」も販売中。例えば朱音の「爆笑とって鼻明かしてやりますから!」という痛快な台詞入りステッカーはファンにはたまらないアイテムです。他にも缶バッジセット**(朱音や師匠のミニキャラ付き)や、美麗イラストを額装したアートボードなど、コレクション欲をくすぐるグッズが目白押し。部屋に飾れば落語会の雰囲気をいつでも感じられるでしょう。
さらに単行本派の方には、電子書籍も含めたコミックス全巻セットがおすすめです。初回特典でクリアスタンドが付属した書店もあり、第5巻発売時には朱音&うららのクリアスタンドが話題になりました。お気に入りのキャラを手元に置いておける嬉しいグッズですね。グッズを手に入れて、ぜひ『あかね噺』の世界観にどっぷり浸ってみてください!
まとめ
『あかね噺』第5巻は、笑いあり試練ありのジェットコースター回でした。朱音の痛快逆襲劇には思わずスカッとし、伝統の壁にぶつかってからの新展開には胸が熱くなりました。まさに「物語が大きく動いた重要巻」と言えるでしょう。個人的な評価を★で表すならば、文句なしの**★★★★★(星5つ)**!落語の魅力と少年漫画の熱さをこれでもかと味わえる神巻でした。
この先、朱音はさらに高いステージへと駆け上がっていくことでしょう。涙も笑いも乗り越えて成長する彼女の姿からは目が離せません。古典芸能を題材にしながら、読めば誰もが熱くなれる『あかね噺』。まだ読んでいない方も、ぜひ手に取ってみてください。次巻もきっと、我々読者の予想を超えるドラマが待っているはずです! 引き続き応援&感想を語り合いながら、『あかね噺』の世界を楽しんでいきましょう。
皆さんは第5巻を読んでどう感じましたか?お気に入りのシーンやキャラについて、ぜひコメントやSNSで教えてくださいね!それでは、最後までお読みいただきありがとうございました✨