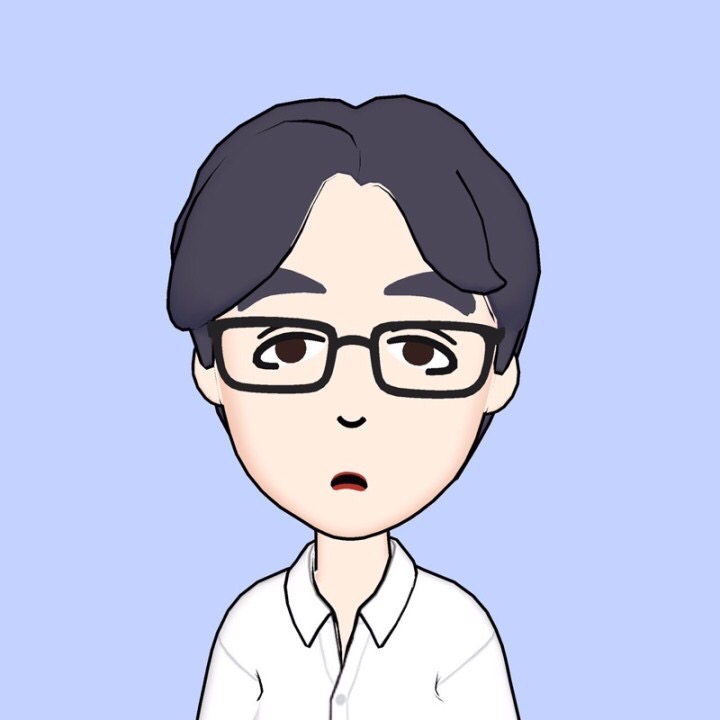「裏染天馬シリーズ」の青崎有吾さんの長編ミステリ『図書館の殺人』。密室トリックと図書館という知的な舞台設定にワクワクしながらページをめくり、読み終えた今も頭の中は謎解きの興奮でいっぱいです。高校の図書館で起きる密室殺人と複数のダイイングメッセージ──ミステリ好きにはたまらない要素がぎゅっと詰まった本作は、期待を裏切らないロジカルな推理劇でした。この記事では、ネタバレを避けつつ本作の魅力をざっくばらんにご紹介します。読後の率直な感想やユニークなトリックへの考察、物語に散りばめられた伏線の面白さなどをたっぷり語りますので、未読の方も安心してお付き合いください。密室の謎に挑む裏染天馬の活躍、一緒に楽しんでみませんか?
著者紹介
青崎有吾(あおさき ゆうご) – 1991年神奈川県横浜市生まれの新進気鋭のミステリ作家。明治大学在学中の21歳で執筆した『体育館の殺人』が第22回鮎川哲也賞を受賞しデビューしました。「平成のエラリー・クイーン」とも称されるほど論理的な推理展開が持ち味で、デビュー以来〈裏染天馬シリーズ〉をはじめ数々のヒット作を発表しています。代表作の一つである本シリーズは、高校生探偵が活躍する本格推理(いわゆる新本格ミステリ)で、その綿密なロジックと意外性あるトリックが高く評価されています。青崎さんは他にも、怪異×推理の『アンデッドガール・マーダーファルス』や不可能犯罪連作『ノッキンオン・ロックドドア』など多彩な作品を執筆しており、『ノッキンオン・ロックドドア』はTVドラマ化もされました。しかし本シリーズでは王道の推理スタイルを踏襲しつつ、ユーモアやサブカルネタも散りばめた独自の作風を確立しています。その緻密なロジックと遊び心は、本作『図書館の殺人』でも存分に発揮されています。
登場人物紹介
主要キャラクターたちを押さえておきましょう。個性豊かな面々が物語を盛り上げます。
- 裏染 天馬(うらぞめ てんま) – 本シリーズの探偵役。風ヶ丘高校2年生。アニメオタクで一見やる気のないダメ人間ですが、推理力と頭脳はピカイチで試験成績も常に学年トップ。普段は百人一首研究会の旧部室に無断で居候する変わり者ですが、ひとたび事件となれば鋭い観察眼と論理で真相に迫ります。警察から“礼金目当て”で捜査協力を頼まれることもしばしば。本作では図書館殺人事件の謎に挑み、持ち前の論理思考で二つのダイイングメッセージを解読していきます。
- 袴田 柚乃(はかまだ ゆの) – 天馬の後輩で風ヶ丘高校1年生(物語当時)。女子卓球部員で明るく行動力のある少女です。シリーズを通して天馬の助手役・語り手的存在でもあり、本作でも主に柚乃の視点で物語が進みます。兄が警察官という縁もあり事件に深く関わり、天馬に捜査協力を依頼することも。天馬の奇人ぶりに振り回されつつも、その才能を誰より信頼している頑張り屋です。
- 城峰 有紗(しろみね ありさ) – 本作から登場。風ヶ丘高校の図書委員長を務める女子生徒。なんと今回の被害者である大学生の従妹にあたり、図書館殺人事件では重要な関係者です。物語では有紗の視点描写もあり、天馬の推理を間近で目撃する立場となります。真面目で知的な雰囲気ですが、事件を通じて天馬の人間味に触れることに…。彼女自身、捜査に協力しながら複雑な心情を抱える役どころです。
- 袴田 優作(はかまだ ゆうさく) – 柚乃の兄。神奈川県警捜査一課の若手刑事です。シリーズでは警部・仙堂の部下として天馬の捜査に半ば呆れつつ付き合う苦労人でもあります。メモ魔でシスコン気味な一面もあり、妹の柚乃が事件に首を突っ込むことには頭を抱えていますが、その妹の頼みで渋々天馬を呼び出すなど、本作でも縁の下の力持ち的に登場します。
- 梅頭 咲子(うめがしら さきこ) – 本作で新たに登場する仙堂警部の部下の女性刑事。年下好きというちょっと風変わりな性格で、高校生の天馬に興味津々(本人は「ロックオン♡」と言っています)というコミカルな人物です。捜査会議でも天馬にやけに親しげに絡んで周囲を困惑させますが、刑事としての勘は確か。物語にユニークな彩りを添えるムードメーカーです。
(※この他にも、風ヶ丘高校卓球部の仲間や他校のライバル探偵、裏染家の妹など個性的な脇役が登場しますが、本記事では主要人物のみ紹介します。)
あらすじ(ネタバレを避けつつ)
季節は9月、風ヶ丘高校では期末テスト期間中。そんな中、学校近くの公共図書館で殺人事件が発生します。早朝、風ヶ丘図書館の館内で男性大学生の死体が発見されました。雨の夜、閉館後の誰もいない図書館に何者かが侵入し、被害者を巨大な本(山田風太郎著『人間臨終図巻』)で殴打して殺害したのです。奇妙なことに、現場には二種類のダイイングメッセージが残されていました。捜査にあたった神奈川県警は容疑者の絞り込みに難航し、かつての事件で世話になった風ヶ丘高校の天才高校生・裏染天馬に協力を要請します。
こうして裏染天馬と袴田柚乃は警察と共に事件捜査に乗り出すことに。図書館で何が起きたのか? 被害者が残そうとしたメッセージの意味とは? 天馬たちは館内の関係者への聞き込みや綿密な現場検証を開始します。被害者の従妹である城峰有紗も事情聴取に立ち会い、動揺しながらも協力を申し出ます。やがて浮かび上がった容疑者は図書館職員(司書)たち。それぞれに怪しい言動や秘密を抱えており、密室状態の館内で被害者と接点を持てた可能性がある人物たちです。天馬は残された“二つのメッセージ”と館内の手掛かりから、彼らの完璧に見えるアリバイや証言の矛盾を突き崩そうとします。
捜査が進むにつれ、新たな謎も浮上します。「なぜ被害者は誰もいない夜の図書館で殺されなければならなかったのか?」密室同然の状況や不可解な行動の背景には、一体何が隠されているのか。事実が明らかになるほど真相が遠のいていくような知識の迷宮に、天馬は挑んでいきます。物語中盤では、お約束の「読者への挑戦」も挿入され、読者も推理力を試される展開です。果たして天馬は論理の糸を手繰り寄せ、事件の全貌に辿り着くことができるのでしょうか──?(※結末はぜひ本編でお確かめください。)
感想
まず一言、「やられた!」と思いました。二つのダイイングメッセージという仕掛けが非常にユニークで、最後までどちらが真実を指しているのか翻弄されっぱなし。定番すぎて昨今では敬遠されがちなダイイングメッセージをあえてテーマに据え、“やっぱり意味があった!?”と二転三転させる展開には思わず唸りました。天馬が論理の糸を少しずつ紐解いていく過程は圧巻で、ページを捲る手が止まりません。図書館という舞台も相まって、まるで知識の迷宮を探索しているような読書体験でした。
本作ではキャラクターの魅力もさらに光っていたように感じます。天馬の飄々とした言動には相変わらずクスリとさせられましたし、彼がたまにボソッと呟くアニメ・声優ネタには思わずニヤリ。(容疑者名に*「桑島法男」*なんて出てきた時は、「もしや桑島法子さん?!」とピンと来てしまい、著者のサブカル愛に笑ってしまいました。)天馬のマニアックな発言に周囲がポカンとする描写もお約束で、緊迫した捜査の合間の良いスパイスになっています。一方で、終盤ではそんな天馬が見せた優しさや葛藤にグッと胸を打たれました。犯人に対してあえて踏み込み過ぎない配慮を見せるなど、彼も成長しているんだなあとしみじみ。今まで論理一辺倒だった天馬が人間味を垣間見せるシーンは、本作の隠れたハイライトと言えるでしょう。
もちろんミステリとしての醍醐味も健在です。図書館ならではの小ネタ(例えば殺人に使われた本のチョイスの絶妙さ!)にもニヤリ。クライマックスの推理ショーでは、散りばめられたヒントが一気に回収され「そう繋がるのか!」と快感すら覚えました。個人的には犯人当てに挑戦しましたが見事にハズレ…。天馬が明かす真相に「やられた!」と脱帽すると同時に、きちんとフェアな手がかりで論証してみせる展開に爽快感を覚えました。まさに論理のジェットコースターに乗ったような読後感で、ミステリ好きには堪らない一冊でした。
考察・解説(ネタバレなし)
『図書館の殺人』は、古典的なミステリのエッセンスと新鮮なアイデアが見事に融合した一作です。青崎有吾さんはこれまでシリーズ長編で「密室トリック」「アリバイ崩し」といった王道テーマを扱ってきましたが、本作では「ダイイングメッセージ」を前面に据えています。ダイイングメッセージというと「非現実的」「ご都合主義」などと言われがちなモチーフですが、本作ではその先入観を逆手に取った巧みなプロットが光りました。犯人が仕組んだ偽のメッセージと被害者が残した本当のメッセージが交錯し、読者も探偵も翻弄される展開は、新本格ミステリの醍醐味を存分に味わえます。作者自身、「ベタなモチーフを現代ナイズしてみせる」ことにチャレンジしたのではないでしょうか。
また、図書館という舞台設定も考察に値します。図書館は「知識の宝庫」であり「静寂の密室」です。本棚や蔵書といった要素がトリックやヒントに密接に絡んでおり、本好きにはたまらない仕掛けが随所に散りばめられています。たとえば犯行に使われた『人間臨終図巻』という書物自体が示唆するものや、特定の本の配置・タイトルが暗号めいて意味を帯びてくる場面など、知識の迷宮を巡るような謎解きに唸らされました。さらに終盤で明かされる犯行動機やトリックの背景には、「本」や「知識」にまつわる意外なメッセージが隠されており、単なるパズルを超えたテーマ性も感じられます(※核心部分は伏しますが、本を愛する人ほどホッとするような真相かもしれません)。
人物描写の面では、裏染天馬という探偵キャラクターの深化が見どころです。前述したように、本作では彼が事件解決に際してある種の葛藤を見せます。論理で犯人を追い詰めるだけでなく、真実を突きつけることで誰かが傷つくことへの配慮も垣間見せました。この変化はシリーズファンにとって新鮮であり、物語に厚みを加えています。推理小説において探偵役の成長が描かれるのは珍しく、本シリーズが単なるトリック自慢に留まらずキャラクター小説としても進化している証と言えるでしょう。
他作品との比較で言えば、学園ミステリで奇抜なトリック…という点では金田一少年の事件簿や『氷菓』などを連想する方もいるかもしれません。しかし裏染天馬シリーズはそれらとも一線を画しています。本格ミステリの王道(エラリー・クイーンや綾辻行人作品のようなフェアな謎解き)を下敷きにしながらも、高校生探偵という青春要素とオタク的ユーモアが融合した作風は独特です。実際、「平成のエラリー・クイーン」の異名どおり、本作のロジック重視の推理劇は古典好きにも刺さる出来映えでありつつ、キャラクターの掛け合いや小ネタは現代的で親しみやすいものになっています。最近では青崎先生原作の別シリーズ『ノッキンオン・ロックドドア』が映像化され話題になりましたが、裏染天馬シリーズも負けず劣らず映像映えしそうな魅力があります。密室トリックに挑む天馬の姿は、まさに現代版ホームズ? いや、アニメ好きを公言する高校生探偵という点で前代未聞でしょう。こうしたキャラクター性と本格トリックの組み合わせは他に類を見ず、本作を含むシリーズ全体の大きな強みとなっています。
読者の反応
SNS上でも『図書館の殺人』は大いに話題になりました。代表的な読者の声をいくつか拾ってみます。
ポジティブな反応(称賛) 🟢
- 「論理の応酬が最高!ダイイングメッセージの真相には鳥肌が立った。天馬くんマジ名探偵」
- 「図書館という舞台がオシャレで知的。読んだら図書館に行きたくなるミステリだった😊」
- 「シリーズ通して読んでるとニヤリとできる小ネタ満載で嬉しい。裏染天馬、今回もブレない活躍でスカッとした!」
- 「終盤の裏染くんの優しさにグッときた…。ただの推理マシーンじゃないんだね。成長描写にほろり😭」
- 「個人的シリーズ最高傑作!伏線回収の鮮やかさでは『体育館の殺人』超えたかも。大満足の一冊✨」
ネガティブな反応(批評) 🔴
- 「ロジックはすごいけど、犯人の動機が弱いかも…。結局何で殺人まで?とモヤモヤ」
- 「最後の種明かし、天馬らしくない遠慮が入ってて物足りなかった…。もっと論破してほしかったかな」
- 「ダイイングメッセージってやっぱりご都合主義じゃ?都合よくメッセージ残せる状況だったのか疑問😅」
- 「新キャラの梅頭刑事がちょっとふざけすぎ?ミステリの緊張感が削がれたという声もちらほら」
- 「『体育館の殺人』の衝撃には及ばないという意見も。一作目のインパクトが凄すぎたせいかな…」
総じて、「トリックが冴えていて面白い!」というポジティブな評価が多く見られました。特に複数のダイイングメッセージの謎や天馬の論理的推理に称賛が集まる一方、物語終盤の演出や動機の描写に関して一部読者から賛否が寄せられています。とはいえ、「シリーズ最高」「続きが早く読みたい!」という声も多く、発売当時はミステリ好きの間で大いに盛り上がりました。
次回への期待
本作『図書館の殺人』は物語として一応の完結を迎えつつも、シリーズ全体を見ると次巻への興味をそそる要素が随所に散りばめられていました。まず、裏染天馬というキャラクターの過去や家庭事情が少しずつ垣間見えてきたことです。天馬がなぜ学校に居ついているのか、父親との確執とは何なのか、気になる伏線が徐々に表面化しており、「次こそ天馬の秘密に踏み込む展開になるのでは?」とファンの期待は高まります。実際、本作では天馬の妹・鏡華など家族に関する情報も断片的に登場し、物語世界がさらに広がりました。次回作ではぜひ天馬の過去や家族に絡む事件が描かれ、探偵としてだけでなく一人の青年としての裏染天馬にスポットが当たることを望まずにはいられません。
また、城峰有紗や梅頭咲子といった新キャラクターの今後の活躍にも期待が募ります。有紗は従妹を事件で失ったことで天馬たちと特別な縁ができましたが、彼女自身が持つ知識や洞察力が次の事件で役立つかもしれません。もしかすると「裏染探偵団」的なチームが結成される可能性も…? 一方の梅頭刑事も強烈なキャラだけに、天馬への執着(?)が今後どう事件に絡むのか見ものです。柚乃や優作刑事との掛け合いも含め、レギュラーメンバーの関係性が今後どう深まっていくのか楽しみですね。
そして何と言ってもシリーズ恒例の「館」もの、次はどんなシチュエーションが来るのか想像が膨らみます。体育館、水族館、図書館と来れば、次は美術館?博物館?それとも全く意外な「○○館」かもしれません。青崎先生のことですから、我々の斜め上を行く舞台設定で新たな密室トリックを用意してくれることでしょう。ファンの間でも「次は〇〇の殺人だ!」と予想合戦が繰り広げられており、続きを待つ楽しみでいっぱいです。
現時点(2025年)でシリーズ新作の刊行は確認できていませんが、著者デビュー10周年も迎えていますし、きっと近いうちに嬉しい報せがあるはず…!裏染天馬の次なる冒険に期待を寄せながら、発表を心待ちにしたいと思います。
関連グッズ紹介
裏染天馬シリーズおよび青崎有吾さんに関連する書籍やグッズをご紹介します。作品世界をもっと楽しみたい方はぜひチェックしてみてください。
- 小説『体育館の殺人』 – 裏染天馬シリーズ第1巻。風ヶ丘高校の旧体育館で放課後に起きた密室殺人事件で天馬が初推理を披露します。記念すべきデビュー作で、この作品で第22回鮎川哲也賞を受賞。まずはここからシリーズが始まります。
- 小説『水族館の殺人』 – シリーズ第2巻。横浜の水族館で起きた飼育員惨殺事件に天馬が挑みます。容疑者はなんと11人!複雑なアリバイトリック崩しに燃える長編推理です。シリーズ随一の大掛かりな謎に圧倒されること必至。
- 小説『風ヶ丘五十円玉祭りの謎』 – シリーズ短編集(第3巻に位置付けられることも)。日常のささやかな不思議から学園祭の事件まで、裏染天馬が挑む連作ミステリ。“五十円玉二十枚の謎”などユニークな小品を通じてキャラクターの新たな一面が描かれています。長編の合間にぜひ。
- 小説『図書館の殺人』 – そして今回レビューしたシリーズ第3長編(文庫版第4巻)。未読の方はこの記事で興味を持ったらぜひ本編を手に取ってみてください。創元推理文庫より発売中です。電子書籍やAudiobook(オーディオブック版)も利用可能なので、自分のスタイルで楽しめます。
- コミカライズ『体育館の殺人 裏染天馬の名推理』 – シリーズ第1作の漫画版。マッグガーデン(MFコミックス)より刊行。天馬や柚乃たちが漫画でどのように描かれているか、ファンならチェックしたいところ。コミックならではの臨場感で名推理を追体験できます。
- 関連グッズ(クリアファイルセット) – 東京創元社のオンラインストアでは、裏染天馬シリーズの単行本カバーイラストを使用したクリアファイル5枚セットが販売されています。田中寛崇さん描き下ろしのスタイリッシュなカバーアート(『体育館の殺人』『水族館の殺人』『風ヶ丘五十円玉祭りの謎』『図書館の殺人』+10周年記念短編集『11文字の檻』)をA4クリアファイルで堪能できます。実用性とコレクション性を兼ね備えたファン必携のアイテムです。
- その他の著者作品 – 青崎有吾さんの別シリーズもぜひ。大正時代を舞台にした怪奇ミステリ『アンデッドガール・マーダーファルス』はアニメ化もされた話題作ですし、現代本格の連作短編集『ノッキンオン・ロックドドア』はTVドラマ化されました。裏染シリーズとはまた違ったテイストで、青崎作品の幅広さを楽しめます。
(上記商品の詳細や購入は各公式サイトや書店にてご確認ください。)
まとめ
シリーズ第3弾にあたる『図書館の殺人』は、裏染天馬シリーズの中でも転機となる一冊だと感じました。論理パズルの切れ味はそのままに、登場人物たちの成長やドラマ性が加わり、物語に深みが増しています。密室トリックの妙味と図書館という知的空間が絶妙にマッチし、新本格ミステリの醍醐味を存分に味わえる快作でした。星5つで評価するならば、個人的には★4.5/5! 綿密なロジックへの驚きと、人間ドラマによる余韻を併せ持った高水準のミステリと言えます。
シリーズ未読の方でも、本作から十分楽しめますが、できれば1作目から順番に読むことでニヤリとできる小ネタやキャラクターの変化をより味わえるでしょう。ミステリ好きの大学生・社会人の皆さん、知的興奮を味わいたいなら裏染天馬シリーズはイチ押しです。ぜひこの機会に読んでみてはいかがでしょうか?
最後までお読みいただきありがとうございます!本作を読まれた方は、ぜひあなたの感想や考察もコメントやSNSでシェアしてくださいね。果たしてあなたは、この図書館の迷宮から真相を読み解けるでしょうか? 解けた人も解けなかった人も、感想を語り合って盛り上がりましょう📚🔍!